もし量子コンピュータがあったら?
山崎 隼汰(情報理工学系研究科/情報科学科兼担 准教授)
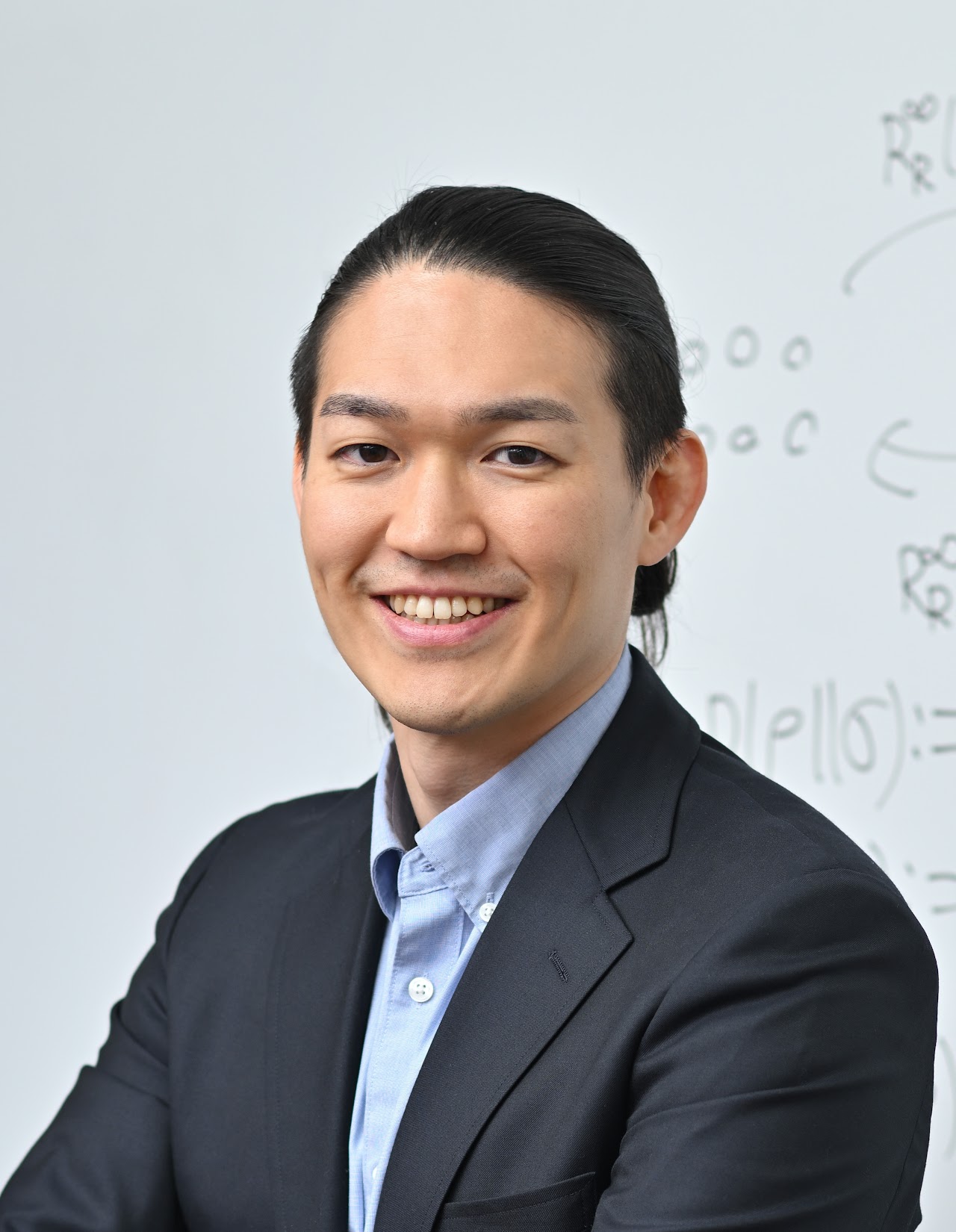
「もし量子コンピュータが実現したら,あなたは何をしたいですか?」そう僕が質問すると,壇上の5人の研究者たちが顔を見合わせた。2024年秋,札幌で僕と共同研究者はワークショップを主催した。世界中から分野を代表する5人の研究者を招き,会場には約100人の参加者が集まった。量子コンピュータ開発の理論や実験の最前線を紹介する講演に加え,パネルディスカッションでは,それぞれの研究者の専門分野から活発な議論が交わされた。
そもそも量子コンピュータとは何だろうか。これは原子や光などミクロな世界を支配する量子力学の原理を利用して,新しい情報処理を可能にするコンピュータだ。私たちが普段使っているコンピュータは,0か1かという「ビット」を単位に計算している。一方,量子コンピュータは「量子ビット」という単位を使う。量子ビットは0と1の「重ね合わせ」状態を取れる。その性質を活かすと,たとえば巨大な整数の素因数分解や複雑な量子現象のシミュレーションといった,従来のコンピュータでは実用的でなかった計算も現実的な時間で解けると期待されている。また,量子通信を通じて従来よりも安全な暗号技術も実現できる。ただし「すべての問題が超並列で一瞬で解ける」わけではない。量子コンピュータの強みが発揮されるのは,計算の裏側に特別な数学的構造がある場合に限られる。例えば素因数分解の場合,数の中に隠れた周期性を量子アルゴリズムが見抜くことで,劇的な高速化が可能になる。一方で,あらゆる問題が量子コンピュータで速くなるわけではないことも,誤解してはいけない点だ。
量子コンピュータの実現にはまだ多くの課題がある。量子ビットはとてもノイズに弱く,計算途中に情報が失われやすい。多くの量子ビットを高精度に制御するスケーラブルな量子コンピュータを作ることは,世界中の研究者にとって大きな挑戦だ。現状のノイズの多い中規模デバイス(NISQデバイス)や量子アニーリングといった方式では,ノイズの影響が抑えられないため,最先端の古典アルゴリズムを超える実用的な高速化は難しい。そこで今,量子エラー訂正によりノイズに打ち勝つ方法が盛んに研究されており,ノイズに強い量子コンピュータを目指した開発が急速に進んでいる。理論の面でも,より効率的な量子エラー訂正や,量子情報処理の有望な応用分野の開拓が進められている。
ワークショップのパネルディスカッションが一区切りつき,司会が「ご質問ある方は?」と会場に投げかけた。こういった場では,最初の一人が名乗りを上げるまで,どうしても遠慮がちになりがちだ。でも誰かが質問すれば,会場の空気が一気に和み,その後は次々と手が挙がりやすくなる。主催者として最初の一歩を促すのも僕の役目。そこで手を挙げ,「もし量子コンピュータが本当に実現したら,あなたは何をしたいですか?」と改めて研究者たちに問いかけた。しばしの沈黙ののち,それぞれの研究者が思い思いの夢を語り始めた。
ワークショップの後,主催した共同研究者たちと打ち上げのジンギスカンへ向かう。「それで君自身は量子コンピュータで何をしたい?」と僕も聞かれる。人類は望遠鏡で宇宙の果てを,顕微鏡で湖の水中にいた未知の動く物体(のちにアメーバやゾウリムシなどと名付けられた微生物)を初めて「見える」ようにしてきた。いずれも,それまで想像すらできなかった世界を可視化した新しい道具だ。量子コンピュータもまた,「これまで計算できなかったこと」を「計算できる」ようにし,人類に新しい世界を見せてくれるツールだと思う。宇宙の果てを覗かなくても,すぐ目の前のミクロな世界に,まだ見ぬ世界を覗ける可能性が広がっている。この新しい道具で,僕たちはこれから何を「見る」のだろうか?
理学部ニュースではエッセイの原稿を集しています。自薦他薦を問わず,ふるってご投稿ください。特に,学部生・大学院生の投稿を歓迎します。ただし,掲載の可否につきましては,広報誌編集委員会に一任させていただきます。ご投稿は rigaku-news[@]adm.s.u-tokyo.ac.jp まで。


