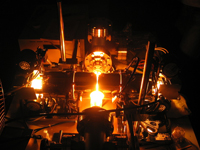歴史
明治10年(1877年)本学部は、徳川幕府の洋学所を濫觴とする。東京開成学校と東京医学校を合併し、東京大学となる 理学部設置数学科、物理学科、化学科(純生化学、応用化学)、生物学科(動物学、植物学)、星学科、工学科(機械工学、土木工学)、地質学科、採鉱冶金学科の8学科を置く。小石川植物園は東京大学理学部附属となる 明治19年(1886年)勅令第3号により帝国大学と改称する 数学科、星学科、物理学科、化学科、動物学科、植物学科、地質学科の7学科を置く。臨海実験所設置 明治30年(1897年)勅令第208号により東京帝国大学と改称する 臨海実験所小網代城址に移転する 明治35年(1902年)植物園日光分園を設置 明治40年(1907年)地質学科を地質学科、鉱物学科の2学科に分ける 大正8年(1919年)勅令13号により東京帝国大学と改称し、理学部に地理学科を設け、星学科を天文学科に改め、理論物理学科と実験物理学科とを合せて物理学科とした 大正12年(1923年)理学部に地震学科を設置 |
|
昭和14年(1939年)人類学科設置 昭和16年(1941年)地震学科を拡充して、地球物理学科を設け11学科となる 昭和22年(1947年)東京大学理学部と改称する 昭和24年(1949年)国立学校設置法公布。 東京大学理学部となり、数学科、物理学科、化学科、生物学科、地学科の5学科が置かれた 昭和33年(1958年)生物化学科設置。地球物理観測所設置 昭和42年(1967年)物理学科物理学課程、天文学課程及び地球物理学科課程は物理学科の拡充改組に伴い物理学科、 天文学科並びに地球物理学科と改称された 昭和45年(1970年)情報科学研究施設設置 昭和49年(1974年)高エネルギー物理学実験施設設置 昭和50年(1975年)情報科学科設置(情報科学研究施設廃止) 昭和51年(1976年)分光化学センター設置 昭和52年(1977年)素粒子物理学国際協力施設設置(時限7年) (高エネルギー物理学実験施設の転換) 昭和53年(1978年)中間子科学実験施設設置(時限10年) 地殻化学実験施設設置 昭和59年(1984年)素粒子物理国際センター設置(時限10年) (素粒子物理国際協力施設の時限による廃止) 昭和63年(1988年)中間子科学研究センター設置(時限10年) (中間子科学実験施設の時限による廃止) 天文学教育研究センター設置 |
|
平成3年(1991年)地球物理学科と附属地球物理研究施設を改組して地球惑星物理学科を新設 分光化学センターはスペクトル化学研究センター(時限10年) 平成4年(1992年)理学系研究科の重点化により、化学、生物化学、動物学、植物学、人類学、地質学、鉱物学の7専攻が改組整備された 数学専攻は独立研究科として数理科学研究科を設置 平成5年(1993年)情報科学、物理学、天文学、地球惑星物理学、地理学の5専攻が改組整備され、 理学系研究科として12専攻すべてが整備された 平成6年(1994年)東京大学素粒子物理国際研究センター設置 (素粒子物理国際センターの時限による廃止) 平成7年(1995年)動物学、植物学、人類学の生物関連3専攻を統合し、生物科学専攻に改組 平成9年(1997年)原子核科学研究センター(研究科附属)設置 (中間子科学研究センターの時限による廃止) 平成10年(1998年)学部附属施設の臨海実験所、植物園、地殻化学実験施設、スペクトル化学研究センター、 天文学教育研究センターが理学系研究科附属施設へ移行
理学系研究科・理学部西棟の竣工 平成11年(1999年)ビッグバン宇宙国際研究センター設置 平成12年(2000年)地球惑星物理学、地質学、鉱物学、地理学の4専攻を統合し、地球惑星科学専攻に改組 平成13年(2001年)情報科学専攻が情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻へ移行 スペクトル化学研究センターの時限延長 生物情報科学学部教育特別プログラム設置(時限5年) 平成16年(2004年)国立大学法人化 素粒子物理国際研究センターの時限延長 平成17年(2005年)理学部1号館中央棟竣工 超高速強光子場科学研究センター設置 アクチュアリー・統計プログラム設置 平成18年(2006年)地学科を地球惑星環境学科に改組 平成19年(2007年)生物情報科学科を設置 平成20年(2008年)遺伝子実験施設は、全学センターから理学系研究科附属施設となる 平成23年(2011年)フォトンサイエンス・リーディング大学院(ALPS)を設置(平成29年度 学生募集終了) 平成24年(2012年)小石川植物園(御薬園跡及び養生所跡)が文化財保護法により国の名勝及び史跡に指定される 平成25年(2013年)フォトンサイエンス研究機構を設置 平成26年(2014年)
生物化学専攻と生物科学専攻を融合し、新たな生物科学専攻を設置 平成28年(2016年)
グローバルサイエンス国際卓越大学院コース(GSGC)を設置 平成30年(2018年)
フォトンサイエンス国際卓越大学院プログラム(XPS)を設置(令和元年度 学生募集終了) |
|
令和元年(2019年)変革を駆動する先端物理・数学プログラム(FoPM)を設置 令和4年(2022年)超高速強光子場科学研究センターを改組してアト秒レーザー科学研究センターを設置 令和6年(2024年)クォーク・核物理研究機構を設置 |
代表的な卒業生
真鍋淑郎(2021年 ノーベル物理学賞)
真鍋淑郎先生は、1931年(昭和6年)に愛媛県宇摩郡新立村(現四国中央市)でお生まれになりました。旧制三島中学校(現愛媛県立三島高等学校)を経て、1953年に東京大学理学部物理学科地球物理学専攻を卒業されています。その後大学院に進学され、1958年に理学博士(地球物理学)を東京大学から授与されました。また、同じ1958年に渡米されています。渡米直後は、米国気象局に気象研究員として従事し、その後、1963年に米国海洋大気庁地球流体力学研究所で上級研究員として働き始めます。1968年にはプリンストン大学大気海洋研究プログラムの教授待遇講師にもなられ、活発に研究を進めることになります。1997年には宇宙開発事業団(NASDA)と海洋科学技術センター(JAMSTEC)による共同事業である地球フロンティア研究システムの地球温暖化予測研究領域長に着任されています。その後、2002年に米国プリンストン大学大気海洋研究プログラムに戻られ、現在は上級気象研究者となられています。
南部陽一郎(2008年 ノーベル物理学賞)
南部陽一郎先生は、1921年に東京でお生まれになり、2歳のとき関東大震災で壊滅した東京から父の吉郎氏の故郷である福井市に移り、17歳まで過ごされました。福井市立進放小(現・松本小)、旧制福井中学(現・藤島高)、旧制一高を経て、1942年東京帝国大学の理学部物理学科を卒業されました。卒業後直ちに陸軍に召集されレーダー研究所などに配属された後、終戦を経て、1946年からは東大理学部物理学科の嘱託、助手を務められました。1949年には、新設の大阪市立大学へ移られ、1952年に米国プリンストン高等研究所の研究員として渡米されました。1956年からはシカゴ大学に奉職され、1970年に米国国籍を取得されています。
小柴昌俊(2002年 ノーベル物理学賞 本学特別栄誉教授)
小柴昌俊先生は、1926年(大正15年)に愛知県豊橋市でお生まれになり、神奈川県横須賀市でお育ちになりました。第一高等学校を経て1951年に東京大学理学部物理学科を卒業されました。卒業後は大学院に進学されましたが、1953年米国のロチェスター大学大学院に入学され、1955年にはPhDを当大学の最短記録で取得されました。その後シカゴ大学で研究員を経て、1958年には東京大学原子核研究所の助教授として日本に戻りましたが、宇宙線の国際共同実験のために日本の代表としてシカゴ大学に再度呼ばれ、気球に原子核乾板を搭載した国際共同実験全体の責任者に選ばれました。
江崎玲於奈(1973年 ノーベル物理学賞)
江崎玲於奈博士は、1947年に本学部物理学科をご卒業されました。また、1959年には本学より理学博士を授与されています。江崎博士は、多年にわたり、半導体物理学の分野で卓越した業績を挙げてこられました。
小平邦彦(1954年 フィールズ賞)
小平邦彦先生は、複素多様体という研究分野を創始し、その広く深い研究は代数幾何学、複素関数論、数理物理学といった分野に大きな影響を及ぼしました。先生は太平洋戦争中に研究の道に進みましたが、戦後まもない1949年、数学における頭脳流出第2号(1番目は角谷静夫)としてプリンストンに渡りました。以来19年にわたる在米生活の間に50篇、1400ページにおよぶ論文を執筆しました。
池田菊苗(“うま味”を発見)
現在、「味の素」などの商品名で一般家庭に広く普及しているうま味調味料(成分:L-グルタミン酸ナトリウム)は、東京帝国大学理学部化学科(現在の東京大学理学部化学科)の池田菊苗教授により、1907年に発見されたものです。池田教授が、昆布から抽出したグルタミン酸ナトリウムは、うま味発見の歴史的な資料として化学専攻で受け継がれています。