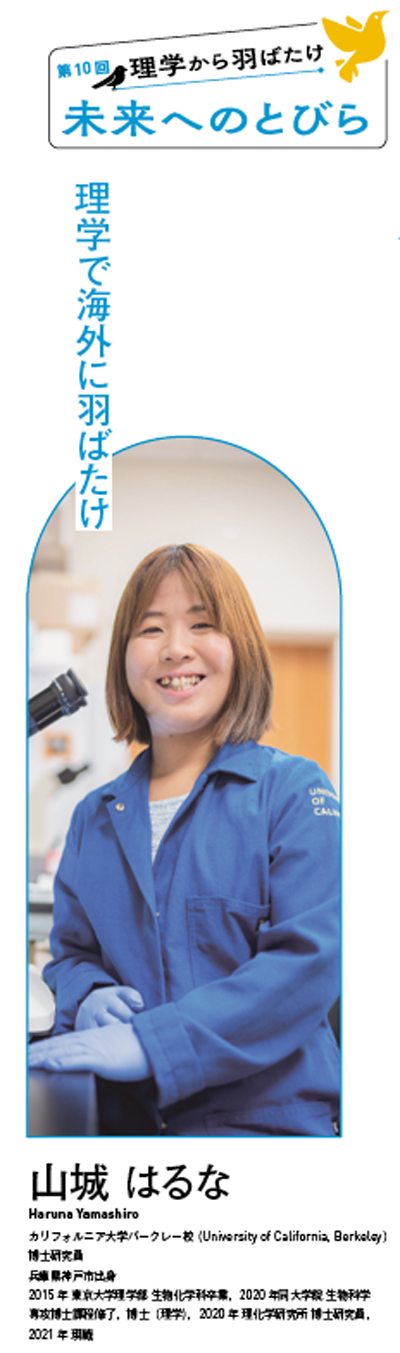
私は生物科学専攻を修了後,理化学研究所での一年間のポスドク(博士研究員)経験を経てから渡米し,現在はカリフォルニア大学バークレー校でポスドクとして研究を続けている。
アメリカでの生活はとても楽しく,幸いにも一度も渡米を後悔したことはない。とくに私がいる西海岸のベイエリアは気候が安定していてとても住みやすい。カリフォルニア特有の広く青い空や,少し足を伸ばせば出会える雄大な自然は,いつも気分を晴れやかにしてくれる。
アメリカでの研究は日本とどう違うか?とよく聞かれるが,実は研究のスタイルに大きな違いはないように思う。日本の研究室と同様に,こちらでも週に一度のラボミーティングで研究室メンバーによる進捗発表や論文紹介が行われる。さらに私の所属研究室ではプロジェクトごとのミーティングや時にはPI(Principal investigator,教授)とのカジュアルな立ち話でより詳細な実験計画について相談し,そこでの議論をもとに実験を進める。また,アメリカでは比較的小規模な研究室が多い。日本の大学の研究室の階層的な構成とは異なって,多くの場合PI一人の元に直接ポスドクと大学院生がついている。そのおかげでラボメンバーの関係性はかなりフラットであり,先輩後輩ということはあまり気にせず助け合ったり指摘できたりするのが個人的には居心地がいいと感じる。

大学で行われた研究会で発表する筆者。ノーベル賞受賞者の教授など多くの方から質問をいただいてとても励みになった
バークレーの一番の長所は,世界中から人が集まってくることだと思う。ほぼ毎日セミナーがあり,国際学会に出かけなくとも著名な研究者の面白い話が聞ける。他の研究室との交流の機会も多くあり,先輩ポスドクからキャリアパスの話などを共有してもらえるランチクラブや,金曜日にキャンパスの芝生広場でひらかれる専攻全体のハッピーアワーなどがある。
またここに来て気づいたのは,誰しもが簡単にアメリカに来られる訳ではないということである。ビザを取るのが困難な国や,母国が紛争に巻き込まれている中,渡米している人もいる。彼らのアメリカで研究をしたいという情熱や,渡米後の具体的なキャリア計画を持つ戦略的な姿勢からは良い刺激をもらえる。
正直なところ,はじめから日本を出ることに積極的な訳ではなかった。英会話にはかなり苦手意識があり自分が海外で働くことは想像できなかったが,夫(物理学科出身)がバークレーでのポスドク先を見つけたことに背中を押され,私も挑戦してみることにした。面接では質問が聞き取れないなど苦労もしたが,運よく今の所属研究室からオファーをもらえた。
おそらく読者の中にも,留学に興味はあるが英語に不安があるという方はいらっしゃるのではないだろうか。でも私たちには英語に加えてもう一つ,理学(サイエンス)という「共通言語」がある。最初は日常の会話はさっぱりわからなくとも,実験の話になんとかついていくうちにその人の英語の特徴がつかめてきて,いろんな話を理解できるようになると思う。サイエンスと英語という二つの共通言語を使って協力して何かが分かった時,日本では味わえなかった喜びを感じるようにも思う。今回の私の文章が留学を悩んでいる方にとって少しでも後押しになれれば幸いであるとともに,自分自身も飛躍していけるよう気を引き締めたい。


