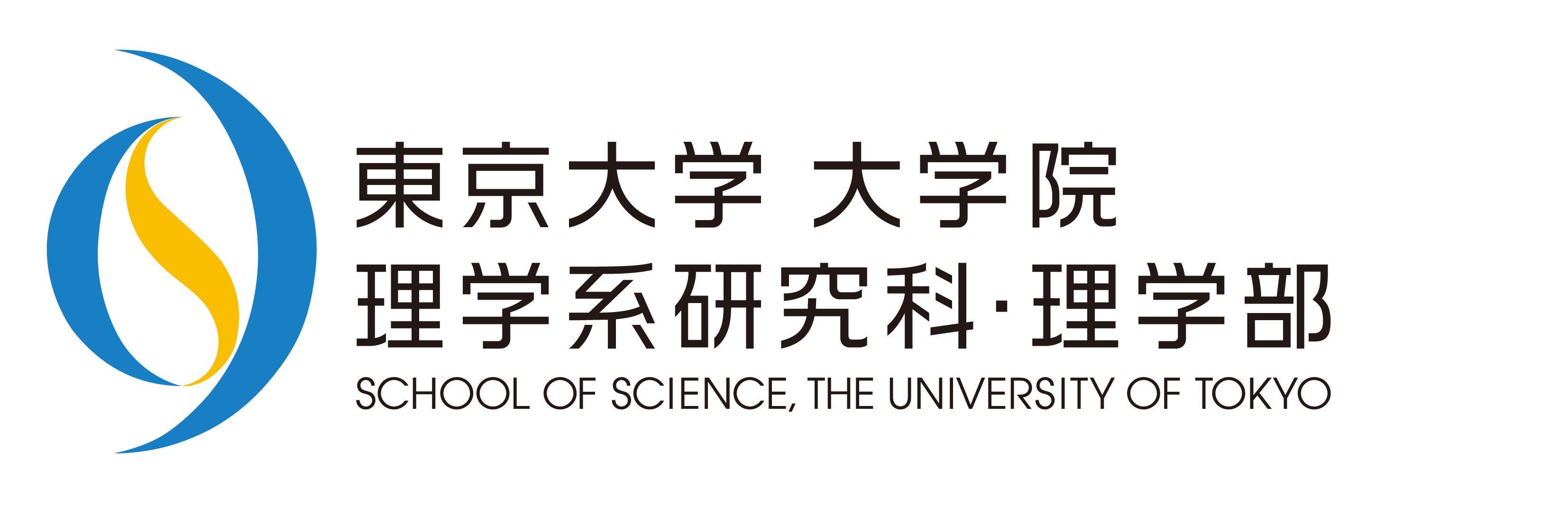日本の近代植物学発祥の地であり、植物研究の世界的センターでもある小石川植物園(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)。戦前のモダニズム建築の傑作とも言われる植物園本館の、歴代園長の肖像画がズラリと壁に並ぶ園長室で、現園長を務める川北教授は、植物はきわめて摩訶不思議な生物であると、こんなふうに言う。
「わたしたち人間は動物なので、動物の感覚で植物を見て、動物の常識を植物に当てはめようとします。そして『植物は動物のようなことは何もできないんだな』というふうに考えるんです。でも、植物は動物とはまったく違う生物で、動物についての常識をはずして植物の目線で見ると、驚くようなことがまだまだたくさん見つかります」
川北教授の専門は植物生態学であり、なかんずく植物昆虫相互作用、つまり昆虫と植物の共生にフォーカスを当ててきた。共生とは、いわば植物と昆虫があたかも世代を越えた意志と記憶を持つかのように、お互いの生存を助け合う、まさに摩訶不思議な関係のことである。その代表的な関係の一つが、たとえばウラジロカンコノキ(コミカンソウ科)とハナホソガ(ハナホソガ属)の共生である。
ウラジロカンコノキは日本では琉球列島に生育する常緑高木で、5月になると枝の付け根のほうに雄花を、先端のほうに雌花をたくさんつける。だが、「緑色の小さな花で、遠くから見ても花が咲いているようには見えません」と川北教授が言うほどとても地味な植物である。

「それなのに、ウラジロカンコノキには花粉を運ぶハナホソガという蛾がちゃんといるんです。ハナホソガは口吻(こうふん)を何度も雄しべにこすりつけ、蜜を取っているような動きをするのですが、花から蜜はまったく出ていません。ハナホソガは蜜ではなく花粉を能動的に集めています。顕微鏡で見るとハナホソガの口にはびっしり花粉がついています。これを今度は雌花に運び、雌しべに花粉をつけはじめます。受粉(雌しべに花粉をつけること)を終えるとハナホソガは産卵管を雌しべに突き刺し、卵を一つだけ産み落とします」
蜜ならわかるが、雄花から花粉を集めて雌花に受粉させるというのは、ハナホソガにとって直接的にはなんの利益もないように見える。まるで送粉(花粉を運ぶこと)・受粉を仕事として請け負ってでもいるかのようなこの行動に、いったいどんな意味があるのだろう。
それはウラジロカンコノキの果実が熟す11月から12月になるとわかる。果実の内部で胚珠を食べて大きくなったハナホソガの幼虫は、果実が熟す頃に果皮に穴を開けて出てきて、地上で蛹になる。果実には6個の種子が入っているが、ハナホソガの幼虫が食べるのはこのうち2~3個だけ。ウラジロカンコノキにとっては子孫を残すには残された種子だけで十分なのである。
つまりこういうことだ。ハナホソガにとって幼虫がウラジロカンコノキの果実の中で成長するには、ウラジロカンコノキの送粉・受粉を行って果実が成るように助けなければならない。一方のウラジロカンコノキは、ハナホソガに送粉・受粉をしてもらうために、ハナホソガに合わせた特殊な花と果実を進化させたというわけである。これぞWin-Win。なんとも驚くべき自然の仕組みではないか。
これが共生という実に不思議な関係、昆虫と植物の生存をめぐる相互作用なのである。
植物と昆虫の接点にある不思議
実はこのウラジロカンコノキとハナホソガの共生関係を最初に発見したのが、加藤真先生という、川北教授が京都大学の学生だった時の恩師なのである。
「とても面白い授業をしてくれる先生がいて、その先生が休講の埋め合わせということで京都の北のほうの山に連れていってくれたことがありました。先生は目をきらきら輝せて、もう片っ端から植物の名前と、それについてる虫との関係を教えてくださって、なんて面白いんだろうと思ったんです」
その面白い先生こそ加藤真先生であり、これがきっかけで川北青年は週末にはかかさず自転車に乗って京都の山へと植物採集に出かけるようになる。
「山に行っては名前を知らない植物を取ってきて図鑑で調べる。そういうことを毎週のようにしていました。ラーメン屋さんのアルバイトでお金が貯まると、夏休みに山梨県の櫛形山や信州の白馬岳にテントをかついで行っては山の上で泊まる。採取した植物を下宿に持ち帰ると、『少年ジャンプ』に挟むんですよ。あれ、すごい吸湿性がよくて(笑)。とにかく、まだ見たことのない植物を見たい。だから、そういうのが生えていそうなところを狙って行くんですね。『青春18きっぷ』を使いまくりました。鈍行で行けるとこまで行こうって(笑)」
中学、高校とサッカー三昧でピッチを駆けまわっていた青年が、“面白い先生”に出会った途端、あっという間に野山を駆けまわる植物学者になってしまったのである。
そんな川北青年が最初の論文となる新発見をしたのが大学2年の時である。
「冬のことでしたが、『先生、今の時期、何を見に行ったらいいですか?』とお聞きしたら、鹿児島や琉球列島に生えているツチトリモチっていう植物は、花粉を運ぶ虫がまだわかっていないから調べてみたらどうだっておすすめいただいて、それで調査を始めました。テントかついで沖縄本島に行って、山の中で何泊もしながら、その花を森の中でずっと観察し続けました。地面からぼこっと出てくる10cmぐらいの植物です」
山にこもること2週間。3日に一度、村に降りて銭湯につかる。それ以外は、ただひたすらその植物を前にして観察を続ける。
「虫は夜に来るかもしれないので、24時間観察を続けて、寝て、起きたらまた観察を始めてという感じです。眠気に襲われながらずっと待っていたらやって来たんです、虫が。一気に興奮して写真を撮ったり、何してるんだろうと目をこらしたり。その瞬間がなんといっても面白くて。だから、寝ずの観察も苦にならないし、楽しいんです」
この研究は3年になっても続け、ツチトリモチの送粉はメイガという蛾が担っているという新発見を、川北青年は論文にまとめる。
「植物の研究なら植物だけ、昆虫の研究なら昆虫だけという人が多いと思いますが、植物と昆虫の接点のところにはまだ誰にも気づかれてない現象がたくさんあると思います。恩師の加藤先生は子どもの頃から貝をたくさん取って集めていたというような方で、植物もわかりますし、昆虫もわかるし、海の無脊椎動物のこともわかる。だからこそ、植物の新種も昆虫の新種も貝の新種も魚の新種も見つけています。ウラジロカンコノキとハナホソガの共生の関係に気づくことができたのも、植物だけでなく昆虫についての深い知識が加藤先生にあったからこそです。そういう先生に教えていただいたというのが大きかったと思います」
現場を自分の目で見ることの大切さ
とはいえ、植物と昆虫の関係を博物学的に記録することが川北教授の研究の本質ではない。植物の形態はなぜこんなにも多様なのか。その形態はどんな進化の道をたどって出来上がったのか。この根源的な疑問に答えること。それが川北教授が追い求めるものだ。

「ウラジロカンコノキの花は本当に地味で、植物学者でもよほど変わり者でなければ研究しようとも思わないような小さな花です。でも、まるで退化したかのように見えるその花が、実はハナホソガという特別な虫と共生するための進化の結果だった。そんなふうに、昆虫などの動物、あるいは外界との関係に応じて花の性質は必然的に決まっていくことがわかりました」
たとえばキキョウの仲間のツルニンジンは下を向いた釣り鐘型の花をつける。この花にはスズメバチだけが集まり、背中に花粉をべったりと付けて送粉をする。花の奥には大量の蜜がある。だが、なぜかアリが食べに来ることはない。不思議に思って学生と調べると、ツルニンジンの花の表面は滑るようになっていて、アリは歩くことができずに落ちてしまうということがわかった。つまり送粉に役立たないアリに蜜を盗まれるのを防ぐために、表面が滑る花を持つに至ったというわけである。
花だけではない。葉の形にも不思議がある。
「ハクサンカメバヒキオコシというシソ科の草木の葉は、深い切れ込みが左右2カ所あるという変わった形をしています。この形はオトシブミという昆虫を惑わす働きがあると私たちは考えています。オトシブミは葉っぱを二つに折り曲げ、先端からくるくる巻いて揺りかごを作ります。ところがハクサンカメバヒキオコシの葉ではオトシブミは葉を巻こうとしないのです」
オトシブミは揺りかごを作る前に葉の上を歩いて“測量”をする。そして、葉の形や大きさなどに不都合なところがないかを確かめてから揺りかごを作り始める。ところが、ハクサンカメバヒキオコシの葉には切り込みがあるため、オトシブミは葉の縁に沿ってまっすぐ歩くことができない。それで、これは普通の葉ではないと知って、揺りかごに使用するのをやめてしまうのである。
こういった昆虫と植物の奇妙な関係は数多く見つかっているが、まだわからないことだらけだと川北教授は語る。
「私たちの研究はどれも最先端の技術を使うわけではありませんが、肉眼で見てわかるレベルのことでも、私たちが植物の多様性について知らないこと、気づいてないことがとてもたくさんあるんです。たとえばイチョウの葉、サクラの葉、カエデの葉、形がまったく違いますが、その形の意味はまだわかっていません。植物について“当たり前”と思っていたことが、実は昆虫との関係で理解できるとしたら面白くないですか?」
植物の形態の進化の道筋、進化の原動力を探るには、観察の範囲は当然世界中におよび、多くの国や地域を、あたかも若き日の野山のように川北教授は駆け回ってきた。
「ニューカレドニアは固有の植物のグループや、世界で一番古い系統の植物があったりして、とても面白いですね。南米のペルーはそもそも植物相がまったく違いました。とにかく研究室にいるとどこかに行きたくなるのは、学生の頃と変わりません。研究室にいる私は偽者の私みたい(笑)。机の上で考えて思いつくようなことには限界があるもので、世界のどこかで誰かがやっていることであったり、それ以上に広がっていかないものであったりするように思います。ある植物のことをふらっと調べに行ったら、その横に生えていた別の植物を見て、もしかしたらこういうことかもしれないと気づいて、そこから広げていく研究がいいテーマになったりするのです。自然界の植物の多様性を理解したいというのが私の大きなテーマですが、何か計画的にやっていくという感じではないかもしれませんね」
そうやって旅の果てに出会うのは、またしても驚異と不思議。
「現実のこういう不思議な植物と動物の関係は、進化の結果だと理解するしかないのですが、そのプロセスを考えると、こんなことが突然変異の連続だけで出てくるものなのだろうかと思う時がたくさんあります。でも、エベレスト山もプレートがぶつかり合って途方もない時間をかけてできたわけで、その連続的な過程は一つずつ追えないかもしれませんが、生き物も同じぐらいの時間スケールで変化し続け、にわかに進化の結果とは信じられないような素晴らしく魅力的な姿を私たちに見せてくれているのだと思います」
学生たちへのメッセージも、もちろん川北流である。
「今はインターネットの世界でいろいろ見ることが多いと思うのですが、それは他人の知識を使って作られた世界です。そうではなく、実際に自分で現場に行ってモノを見るということを学生のうちにたくさん体験してください。それができれば、学生時代の過ごし方としてはとてもいいんじゃないでしょうか」
そう語る目の輝きは、自転車で京都の山々を駆け巡る青年のそれであった。
※2022取材時
文/太田 稔
写真・動画/貝塚 純一


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)