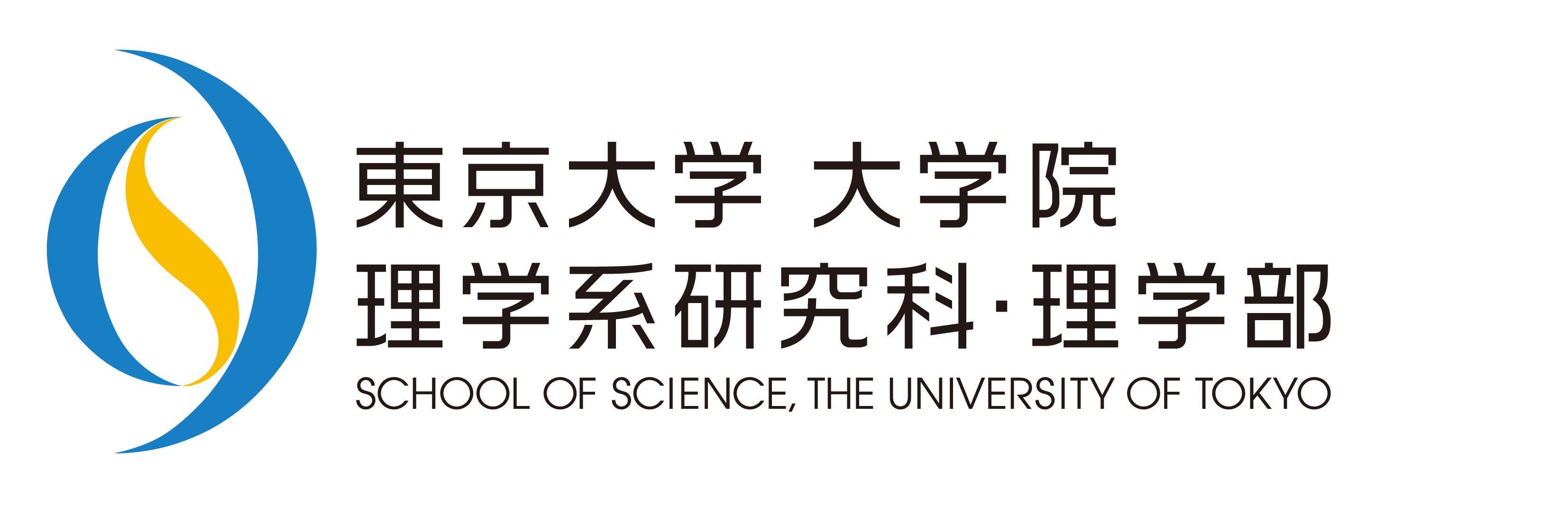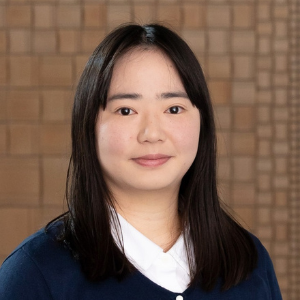66台のアンテナをつなぎ、彼方の宇宙を見通す電波望遠鏡「アルマ」。
最新鋭の望遠鏡を駆使する気鋭の研究者は、星と惑星の形成過程の謎に迫る。
南米・チリにあるアルマ望遠鏡は、日米欧が国際共同で建設した世界最大級の電波望遠鏡だ。66台のアンテナで天体を観測し、それらの受信データを組み合わせ、最大で口径16kmの電波望遠鏡と同じ解像度を実現できる。解像度が上がるほど、宇宙の中のより小さな構造を見分けられる、つまり視力が良くなるのだ。
「アルマ望遠鏡を使って、生まれて間もない星を観測しています。恒星や惑星が誕生する現場は低温のガスや塵の雲の中、可視光では雲に隠されてしまいますが、雲を透過する電波を観測すれば内部を見通せます。また、ガス中のさまざまな分子は特有の波長の電波を出すので、星や惑星の誕生現場にどんな分子があるのかも分かります」
そう解説する物理学科の大屋助教は、星・惑星系形成分野の研究で画期的な成果を次々と挙げている。
「博士論文では、原始星の周囲にある『原始星円盤』の化学組成を明らかにしました。円盤の外側と内側とで化学組成が違うことを突き止めたのです」
原始星円盤からは、最終的に惑星系が作られる。その化学組成が全体として一様ではないことは、最終的にできる惑星の組成にも大きな影響を与えるはずだ。
このように、大屋助教の研究対象は天文分野だが、所属は天文学科ではなく物理学科である。研究室のテーマは「宇宙物理学」だ。物理学者として天文現象を研究する意味を、大屋助教は次のように語る。
「興味があるのは、さまざまな天文現象の背後にある物理法則です。私の印象として、天文学者は個々の現象の“特殊性”に注目する傾向がありますが、物理学者はあらゆる現象に共通する“普遍性”を見つけ出そうとします。両者には、アプローチや視点の違いがあるように感じます」
そもそも、大屋助教は宇宙物理の研究をしようと思っていたわけではなかった。
「高校生のころから数学や物理が大好きで、進振りの時には数学か物理かで悩んだ末に、物理学科を選びました。進路として天文学科はまったく考えていませんでした」
宇宙物理の研究をするようになったのは、大学院進学の際の研究室選びがきっかけだ。
「指導教官である山本智教授の人柄に惹かれて研究室を選び、そこの研究テーマが宇宙物理学でした」
物理学科では、「2年間座学中心で、物理の基礎を徹底的に叩き込まれた」とのこと。
「学科で培った基礎力が、今も活きています。大学院から宇宙や天文を学び始めたわけですが、天文学を専門に学んできた人たちとも同等に渡り合えている手応えがあります。大学院に進学せず民間企業に就職した友人たちも、学科での勉強が身になっていると話しています」
今後は、「さまざまな星や惑星系の形成・進化の過程の根底にある基本法則を見つけたい」と語る大屋助教。
「普遍法則に迫るのが、理学や物理の楽しさであり、研究のモチベーションです。今は星・惑星系形成を研究していますが、将来は研究分野を変える可能性もあります。分野が変わっても対象が変わるだけで、多種多様な現象をシンプルに説明する理論を見つけたいという思いは変わりません」
※2020年理学部パンフレット(2019年取材時)
文/萱原正嗣、写真/貝塚純一


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)