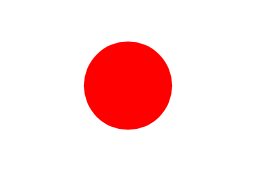最大のスケールから…
科学と自然はいつも私の周りにありました–––。私は、活火山の桜島で有名な鹿児島県の出身で、小規模な火山噴火を見るのは日常茶飯事でした。また、日本の都市部から遠く離れた鹿児島の夜は、いつも満天の星空が輝いていました。このような自然豊かな鹿児島には、ロケット発射場を備えた種子島宇宙センターもあります。桜島の火山噴火とは相反して、ロケット打ち上げはとても稀なことです。何年も前のことですが、暗い朝の空に輝くロケットを家族と一緒に見たことは、今でも鮮明に覚えています。こうした経験が、私を科学、とくに宇宙への興味へと導くきっかけとなりました。
中学・高校では、宇宙を理解するには素粒子と呼ばれる小さな要素が不可欠であることを学びました。こうして私の興味は物理学に移り、高校生の時に筑波の高エネルギー加速器研究機構(KEK)を訪れたことでさらに強まりました。粒子加速器の非現実的な巨大さに圧倒され、実験物理学へと惹かれた私は、東京大学の多くの研究者が粒子加速器を使った実験をしていることを知って、東京大学で学びたいと思うようになりました。また、高校時代には多くの研究室にも足を運びました。科学者たちが楽しそうに仕事をしている姿が印象に残っています。これらの経験が、私の物理学者になる夢を形作り、大学院で研究を続けることは自然な選択でした。
…最小のスケールへ
私は原子核実験物理学を専攻し、現在は物質の小さな単位である原子核の構造を研究しています。物質の「内部」、原子のレベルを超えたさらに微小な世界では、原子核と電子を「見る」ことができます。原子核は陽子と中性子で構成されていますが、それだけでなくラムダ粒子といった「奇妙な」粒子を組み込むことも可能です。私が所属する中村哲研究室では、中性子、陽子、そして「奇妙な」粒子がどのように相互作用するかを測定することを目指し研究しています。この研究分野は高エネルギー原子核物理学と呼ばれています。高エネルギー粒子を用いて、原子核から粒子を叩き出し、放出された粒子を測定することで、原子核の構造を推測します。しかし、測定を成功させるためには、多くのタスクを完了する必要があります。その一つが、実験で使用される高エネルギー粒子のビームを作ることです。
ビームに焦点を当てて
前述のように、原子核を調べるためには、入射粒子(原子核に向かって打ち込む粒子)とノックアウトされた粒子の両方から「逆算」して原子核を調べます。これは、放出される粒子だけでなく、入射粒子、つまり実験で使用されるビームを構成する粒子も、正確に測定する必要があることを意味します。ビームの正確なデータがなければ、原子核に対する推測が間違ってしまう可能性があります。これが私の現在の研究テーマであり、いかにしてビーム自体の正確な測定ができるか、その方法を探っています。さらに興味深いことに、この研究テーマは私が見つけたのではなく、むしろ“私に見つけられ”たのです。最初は、指導教員から割り当てられたタスクの一つに過ぎませんでした。しかし、過去2年間この分野を研究するうちに、多くの複雑な問題が関連して発生することに魅了され、のめり込んでいったのです。この研究テーマは、実験物理学者を目指す私の興味にも合致していました。理論物理学の美しさも魅力的に感じてきましたが、私が面白さを感じるのは、現実に対して理論を実験的に検証できるかどうかです。このような検証は時に複雑な結論を導くこともありますが、理論の美しさと現実との対応関係を発見したときの喜びは、この上ないものなのです。

ユニークな「品質管理」の方法
実験を可能にする良質なビームは、直径が小さく、ビーム全体で非常に安定したエネルギー分布を持っています。「奇妙な」原子核を作るには、電子ビームと重い粒子(中間子)ビームの両方が用いられます。電子はそれ自体を直接加速してビームとして利用できますが、重い粒子(中間子)は他の種類のビーム(陽子など)によって生成する必要があるので、調整と制御がより困難です。そのため、私たちの研究室では精密な測定を目的として電子ビームを使用します。この私たちの独自の方法は、世界で最も高い精度を実現できます。私たちの結果には更なる議論が必要だと考える研究者もいますが、私たちは自信を持っており、新しいデータを収集し続け、この手法の有効性を実証したいと思っています。この手法では、電子ビームが曲がるときに受ける加速によって可視光を含む放射を引き起こす性質を利用しています。私たちはこの放射光を観測し、ビームのエネルギーに関する情報を抽出することで、ビームの品質を保ちます。このような光の観測方法は、レーザー物理学などの研究分野では確立した手法ですが、ビームエネルギーの測定に応用したのは私たちが初めてです。現在は、この春にドイツで収集したデータの分析に取り組んでいます。
物理学者が集うマインツでの経験
私はとても幸運なことに、研究室のサポートによって、ドイツのマインツに行くことができました。マインツ大学(正式名称:ヨハネス・グーテンベルク大学マインツ)には、マインツ・マイクロトロン(MAMI)という有名でユニークな電子粒子加速器があります。加速器は大きすぎて移動できないため、私たち研究者が移動して研究します。私はマインツの加速器で働く、多くの原子核物理学者や素粒子物理学者の一人となりました。前述のように、私が所属する研究室は高エネルギー物理学実験に使用されるビームのエネルギーを測定する独自のユニークな方法を開発しました。私はこの方法の精度を実証するために、ドイツで彼らの設備を使用してデータを収集しました。このプロジェクトは、物理学者と加速器チームが密接に協力し、原子核物理学の新発見と、ビーム物理学の新手法を同時に確立するという初めての試みでした。そのため、私は測定が正確に行われるように加速器の制御や測定を主に担当し、他のコラボレータは核物理学実験自体に集中しました。そして、実験の詳細について毎日数時間の議論を行いました。この楽しかった期間の中で、二つの鮮明な記憶があります。
ある時、粒子検出器が故障して測定を続けることができなくなりました。私たちは実験の重要性を主張し、ドイツのホスト教員に検出器の修理を依頼しなければなりませんでした。私たち学生だけでは思うように話を進めることができず、日本の指導教員に連絡をとり、どのように進めると良いか相談しました。指導教員がこの問題についてドイツのホスト教員と議論する様子を見ていると、日本とドイツの文化の違いに気付きました。ドイツの研究者は問題が発生しても就業時間内までには作業を切り上げ、翌日にはきっと解決できると自信を持って言います。日本の研究者であればそうはならないでしょう。ドイツの研究者は日本の研究者よりも楽観的であるという違いが興味深かったです。
加速器は24時間365日体制で稼働することがよくあります。私たちは6時間のシフトで働き、時には真夜中に働くこともありました。マインツの加速器では、日中は上級スタッフが研究戦略を決め、夜間のシフトは若いメンバーの自主性に委ねられるという文化があります。そのため、同年代の若い研究者と一緒に働くことが多く、真夜中という時間帯もあり和気あいあいとコミュニケーションを取ることができたと感じます。マインツでの経験は、本当に素晴らしいものでした。

学生へのアドバイス
学部生になると、単に試験に合格するためにいくつかの科目を勉強しなければならないと感じることがあるかもしれません。あるいは、学校でいろんな科目の授業を聞いているときに、そのような気持ちになったことがあるかもしれません。しかし、もしあなたが本当に興味を持っていることを勉強しているなら、教授が教えていることは、その分野の一つの視点に過ぎないということに気づくでしょう。たとえば、同じ知識でも研究室と実験室では異なって見えることがあります。これは理論家の視点と実験家の視点の違いとも言えるかもしれません。カリキュラム全体にも同様のことが言えると思います。研究室や教室の枠にとらわれず、自分の興味のあるテーマを自由に探求してください。その発見は、あなたの学びのモチベーションをさらに高めてくれるはずです。同じ「発見」の精神は、海外での経験で得られることもありますから、ぜひ海外にいくことを恐れないでください。実はドイツへの渡航は、私にとって人生で初めての海外経験でした。しかし、FoPM(Forefront Physics and Mathematics Program to Drive Transformation)のおかげで、多くの先輩たちと話すことができ、海外での研究について話を聞き、その一歩を踏み出す勇気となりました。ドイツ語を話せなかった私は、研究所の外でのコミュニケーションに苦労することもありましたが、「bitte」(ドイツ語で「お願いします」)という魔法の言葉を発見し、さまざまな状況を乗り切ったことは良い経験です。海外での経験はきっとあなたの糧となる素晴らしい経験となるはずです。挑戦をためらっている学生には、ぜひ挑んでほしいと思います。
※2024年取材時
撮影/長谷川 博一
英語取材・文:ベルタ エメシェ(訳:武田加奈子)
文章は簡潔にするために編集されています。


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)