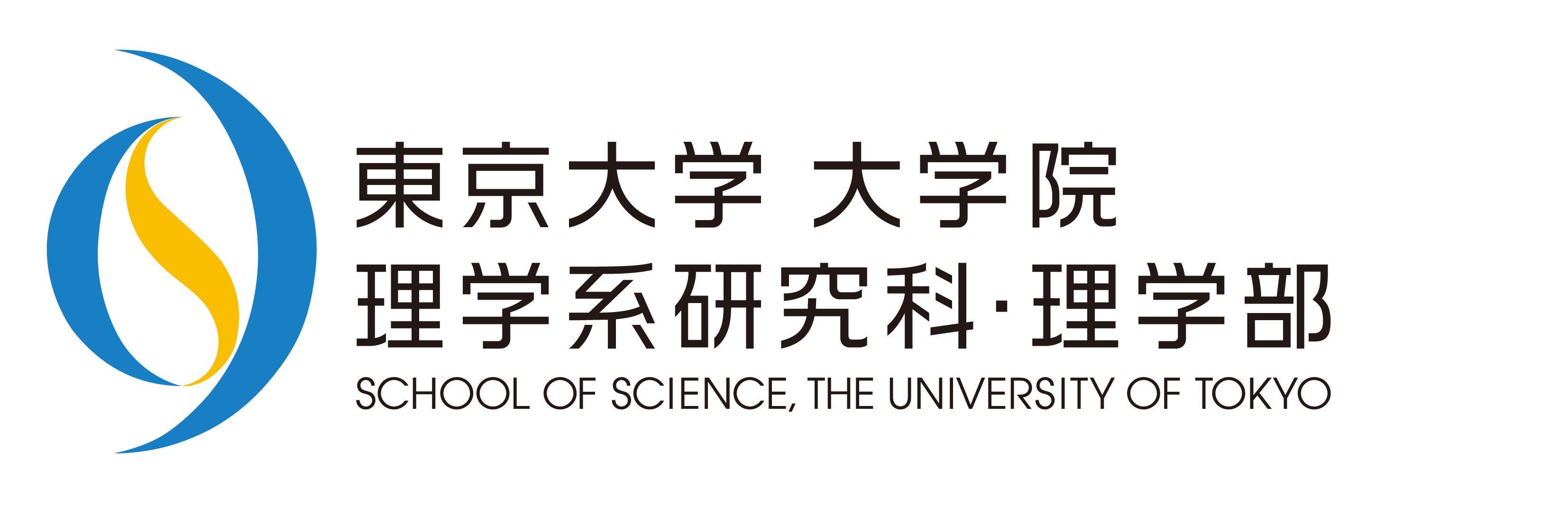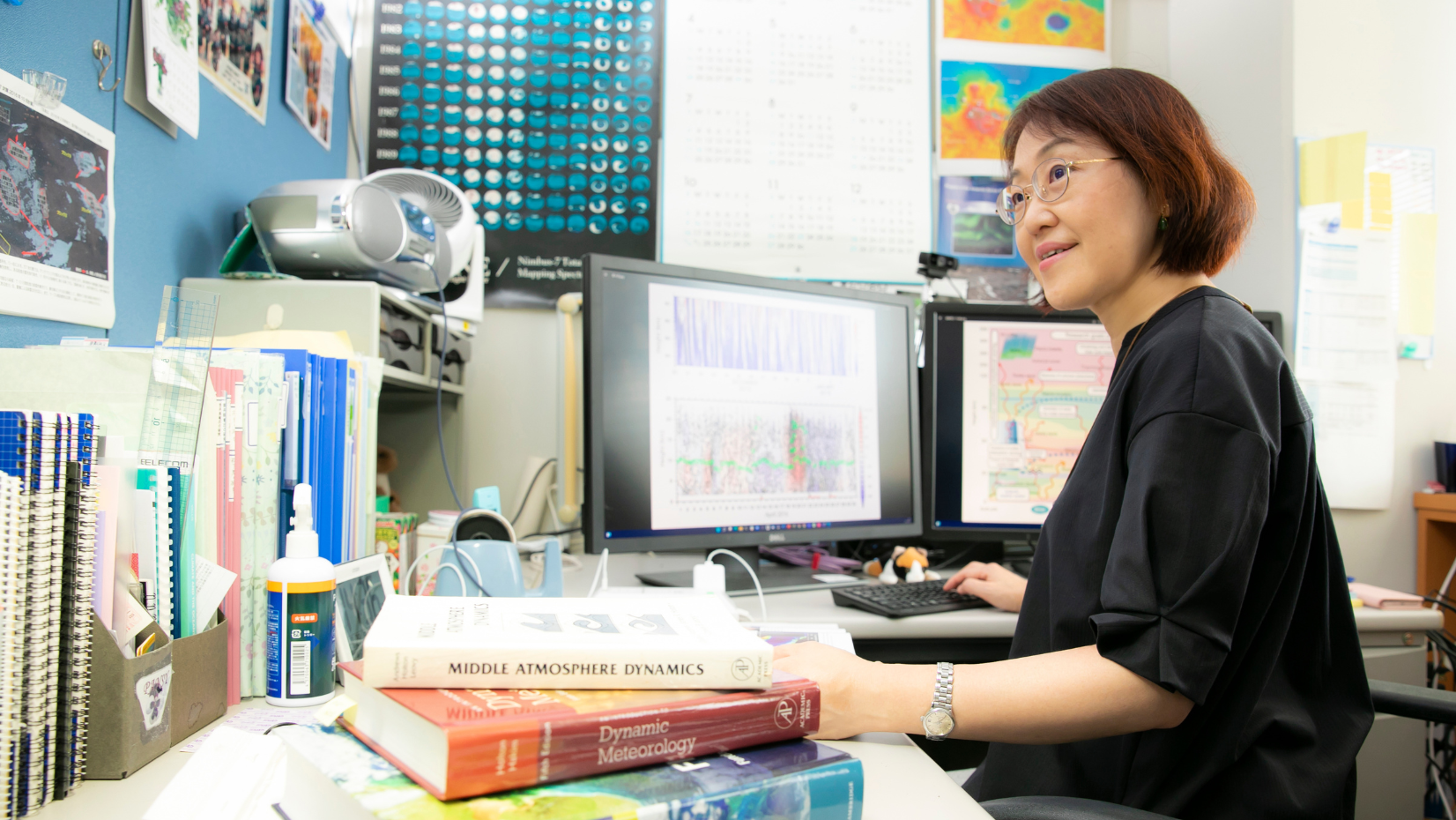さまざまな困難や軋轢を乗り越えて「一番おもしろい」と思うことをやる……。
言葉で言うのは簡単だが、なかなかこれが難しい。誰だって現実の厳しさを跳ね除けて「思い」を遂げることの難しさを感じている。気象学者、佐藤薫教授はそれをやり遂げてしまった人だ。いや、やり遂げたというより現在もそれは続いている。
「メインの研究テーマは大気重力波です。気象学では『大気中の浮力を復元力とする周期数分から十数時間の波』のことを大気重力波と呼んでいます。大気の運動の中では小さな波なのでかつては研究することが難しい現象でした。私は大学院生だった頃から、その大気重力波の研究を続けています」
メインテーマを見つけてから現在に至るまで、彼女はどのように研究への情熱を貫いてきたのだろうか。
理系科目好きから拓かれた気象学者への道
小学生の頃から算数と理科が好きで得意だった。理系科目好きは中学・高校も変わらず、東京大学に入ると、気象学の門を叩いた。なぜ、気象学だったのだろう。
「いろいろな学科の中で地球物理が一番おもしろそうでした。その地球物理の中で『もっとも物理物理しているな』と思って選んだのが気象学だったんです」
気象学者、松野太郎博士(佐藤薫研究室の先々代の教授)の講義が非常におもしろく、物理物理している気象学にのめり込んでいった。そして、修士論文をまとめる過程で「自分は研究がとてもおもしろいと思う人間なんだ」と思った。しかし、博士課程には進まず、企業(NEC)に就職し研究所に配属された。研究所での仕事は、それはそれで充実していたのだが、やはり自然科学研究への憧憬を諦めきれず、結婚を機に退社。京都大学の博士課程に進学した。
「NECは女性が仕事をするのにとても良い環境でしたから、せっかく入社させてもらった会社を辞めることは私にとってかなりの決断でした。大きな決断をしたのだから、もう研究者になるしかないなと腹を括りました。京大ではすごく勉強したし、すごく研究したし、また、すごく楽しかった。中学・高校の頃から漠然と『研究者ってかっこいい』と憧れていたのでその仕事に近づいていることがうれしかった」
前述したように大気重力波はとても小さな波だ。当時だけでなく現在でも天気予報モデルでは十分に解像できないほどだ。しかし、大気重力波が運ぶ運動量は大気の変動において重要な役割を担っている。1980年代、解像はできなくても天気予報モデルに大気重力波の作用をパラメータ化して組み込むようになると、それまでとは段違いに当たるようになった。ちょうどその頃、観測技術もスーパーコンピュータの性能も上がってきて、いよいよ重力波をちゃんと研究しようという流れとなった。大学院生時代およびポスドク時代に一貫してMUレーダー(京都大学生存圏研究所が信楽に設置した大気観測用大型レーダー)を使った中緯度地域上空の大気重力波研究を行ってきた彼女は、京大の助手となり、ほかの緯度帯にも研究対象を広げた。
「中緯度では論文を10編くらい書きました。そして、次に赤道上空の大気重力波研究を始めました。この赤道の研究は国際的にかなり盛り上がり、赤道成層圏準2年周期振動と呼ばれる気候学的にも重要な大規模振動の大きなシナリオ転換にも貢献できました。そして、中緯度、赤道ときたら今度は極域だろうということで、北極と南極の大気重力波研究を始めました。すると、国立極地研究所で助教授の公募があるので応募してみないかと誘われたんです。極地研に行けば実際に南極に行って観測できるかもしれないと思って応募しました」
こうして、彼女は極地研で2人目の女性の助教授として採用されたのだった。
南極に巨大な大気レーダーを
「極地研ではほとんどの先生方が男性なので、当然、女性の助教授は注目されます。そこで『最初が肝心だ。何か大きなことを言ってやろう』と思い、着任して最初の自己紹介を兼ねた研究セミナーで『南極に大型大気レーダーを作るといいと思います』と提案しました(笑)」
たしかに大きい話だ。それを最初から「大きなことを言ってやろう」とたくらんで言うところがお茶目である(笑)。しかし、彼女にとっては大真面目な話だった。南極では充実した大気観測環境がないので、それまではいわば手探りの観測だった。大型大気レーダーの設置は南極大気観測をしっかりした精密科学に発展させようという野心的な提案だったのだ。
「そのセミナーの後、研究主幹(副所長クラス)の先生が私の居室にいらっしゃいました。そして、『さきほどのレーダーの話、検討してみなさい。私がバックアップするから』と言ってくださったんです。来たばかりの女性の助教授にそんなことを言ってくださるなんて、『なんと懐の深い組織だろう』と感動しました。この時から南極の大型大気レーダー『PANSY(Program of the Antarctic Syowa MST/IS Radar)』の設置プロジェクトが始まりました」
このPANSYを南極に設置するまでに10年かかった。大掛かりな設備なので建設に時間がかかるであろうことは確かだが、それにしても相当大変な仕事だったのではないか。
「まさに、三重苦というかんじ。三重苦のひとつめは技術的な困難でした」
技術的困難の克服は多岐にわたった。まずは、電力問題。大型大気レーダーを動かすには230kWの電力を必要とする。しかし、南極・昭和基地で使える電力は基地全体で200kWほど。つまり基地全体の電力を止めてもまだレーダーを動かせないほど電力が必要なのだ。当然、使用電力の削減という技術革新が必要だった。それから、アンテナの重量や形状。この大型大気レーダーは3mの高さのアンテナを約1000本並べる構造になっている。アンテナ1本の重さが50kg。南極では研究者がすべて自分で設置することになるが、自分の体重と同じくらいのものを1000本も運んで設置するのはきわめて困難。だから軽量化は必須だった。
「本当にいろいろな工夫をしました。電力に関しては当時の携帯電話に使われていた高効率のE級アンプを採用することにし、電力ロスが少ないケーブルを開発するなどして85kWで稼働できることを目標に使用電力を下げていきました。さらにこまごまと削減して60kW弱で稼働するシステムができあがりました。また、南極では猛烈な台風並みの強風が毎年1~2回吹きますし、南極大陸斜面を滑り降りるカタバ風というほぼ一定の強めの風が吹き続きます。だから、アンテナは軽くて丈夫なだけでなく、共振が起こらない形状のものを開発しました。その結果、女性でも軽々と持ち運べる12.6kgのアンテナができあがりました」
さらに、南極で建設が可能な1ヶ月強の夏の期間に約1000本のアンテナを設置するためには1本の組み立てが早く終わるものでなければならない。
「最初、京大から提供していただいた50kgのアンテナを南極に持って行って試しに設置してみたんですが、1本組み立てるのに2日もかかりました。だから、メーカーさんといろいろ工夫して『仲の悪い2人組でも1本10分で組み立てられるアンテナ(笑)』を開発しました」
技術革新の成果で、ほぼすべてのパーツが20kg以下で組み立てやすい『人間にも優しいレーダー』ができあがった。ここまで徹底した開発を10年でやるのはむしろ早かったのではないかと思えてくる。
10年をかけて思いを遂げた日々
「三重苦の2つめは『国の南極観測プロジェクトの中期計画に載せる』という仕事です。当初は強い反対意見があって、中期計画に載せるのがとても難しかった。また、同時に三重苦の3つめ、予算取りをしなければなりません。大型大気レーダーを作るには補正予算をつけていただく必要があるのですが、当時は科学・技術に大きな予算がつくのはとても稀だったのです。何度も文部科学省にうかがって話を聞いていただいたり、国際的な学術組織でプレゼンして『この計画はとても重要です』というお墨付き(提言)をいただいたり。レーダーの技術開発は自分たちの努力で進めていけますが、この2つめと3つめは交渉相手次第ですからね。技術開発も7年目ぐらいには、やることが尽きてしまいました」
そこまで行って彼女はどうしたのか。
「死んだふり作戦をしたんです(笑)」
つまり、諦めたふりをしたのだ。PANSYの活動を全て休止し、京大助手時代に少し始めていた高解像度の大気大循環モデルを用いた大気重力波研究に自らの研究の舵を切った。7年間PANSYにほとんどの時間を使ってきたので、このままではまずいかもという、研究者としての危機意識もあった。
「しばらく死んだふり作戦をしていたら……『あんなに元気だったのに、PANSY、どうしちゃったの?』みたいな雰囲気になって徐々に味方が増え、ついには予算がつくことになりました。予算が決まると、今度は『中期計画に載せましょう』という話になって……。昔、社会党の委員長だった土井たか子さんが『山が動いた』という表現をされていましたが、まさにそんなかんじで、状況が変わっていきました」
なんたる劇的展開。世の中は一筋縄ではいかないものだ。思いを遂げるためには実にいろいろな攻め方が必要なのである。
こうして、PANSY設置を実現できることとなったが、レーダーの機材を運び込む段階で2年連続の(2012年、2013年)砕氷船『しらせ』が接岸断念という憂き目に遭ってしまった。
「それでも運び込めた機材で2012年4月から部分システムで観測を開始しました。10年かけて実現に漕ぎ着けて、初めて観測された風のデータを見たときにはPANSYってとうとうレーダーになったんだと感無量でしたね」
結局、すべての機材を南極に運び込み、全システムで観測を始められたのは2015年3月だった。

成層圏突然昇温の影響を解明せよ
かつて、南極大陸は唯一、大型大気レーダーがない大陸だった。佐藤教授はPANSYを実現させ、この壁を越えた。地球の大気は地表から上に向かって、対流圏、成層圏、中間圏、熱圏と大きく分けて4つの層で構成されている。「この4層を貫いて伝播する大気重力波」が佐藤教授の研究テーマである。
「冬の北極の成層圏(高度30km付近)では、突然、数十度も気温が上昇する『突然昇温』という現象がしばしば起こります。この突然昇温は広く北半球の地上気温に影響を与えるのですが、最近、南極の中間圏の上の方(高度90km付近)にも影響を与えることがわかってきました。私はそのメカニズムを解明すべく研究を続けています」
PANSYのような大型大気レーダーは設置が大掛かりでコストもかかるので、世界に何台も存在しない。それでも、極域、中緯度、赤道という各緯度帯に大型大気レーダーは設置されている。そこで、佐藤教授は各大型大気レーダーを所有している各国の研究者に呼びかけ、「成層圏突然昇温が起こった時に各緯度帯の大気重力波はどのように変化するか」を共同で観測することにした。この国際共同観測はすでに7年目となっている。
「現在、PANSY、重力波を解像できる大気大循環シミュレーションモデルなど、ようやくすべてのツールが揃った状態です。今後はこれらのツールを使って研究を展開していこうと思っています」
近年、地球温暖化問題がクローズアップされているが、大気を含む地球システムの研究はまさにこの問題に直結している。
「そうなんです。私は『地球の気候問題は大気領域すべてを視野に入れて研究しなければ』と思っています。気象学で扱う『窒素4酸素1の割合でよく混合された大気』は対流圏・成層圏・中間圏・下部熱圏の範囲に広がっています。つまり、この範囲は大気の運動(風)で全部繋がっているんですよ。だから、この範囲のすべてを把握できれば、大気からの地上への影響をしっかり予測することができるわけです」

地球の大気理論は火星大気に通ず
話を聞いていけばいくほど、気象学者の大冒険は魅力的な物語である。さて、佐藤教授の今後の研究の展望は?
「揃ったツールを駆使して大気全体の解明を続けていきたいですね。それから、最近では学生さんと一緒に火星の大気の研究も始めました」
え! 火星?
「大気理論は地球大気の研究によって構築されてきたわけですが、実は火星の大気にも適用できるのです。特に成層圏・中間圏の理論はほぼそのまま火星大気に適用できます」
これはすごい。佐藤教授の「一番おもしろいこと」は地球のみならず宇宙にまで広がっていくのだ。物語はどこまでも続いていく。
では最後に、この物語を読んでいる高校生や学部生に佐藤教授からのメッセージをいただこう。
「気象学は身近で地球全体に広がる空の現象や大循環を調べる科学です。興味深い研究対象がすぐそこに、目の前にあるのですからおもしろくないわけがありません(笑)。それから、気候や気象は社会と密接に繋がっています。純粋に一番おもしろいことを追究していくと、自ずと社会に貢献してしまう科学なのです。こんな魅力的な分野に、みなさんも足を踏み入れてみませんか」
一番おもしろいと思うことをやり遂げてきた気象学者は、過去の困難などなかったかのように朗らかだ。今日もまた、彼女は南極の空に思いを馳せて大好きな研究を続けている。
佐藤薫研究室HP:https://www-aos.eps.s.u-tokyo.ac.jp/~sato-lab/
※2022年取材時
文/清水 修
写真/貝塚 純一


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)