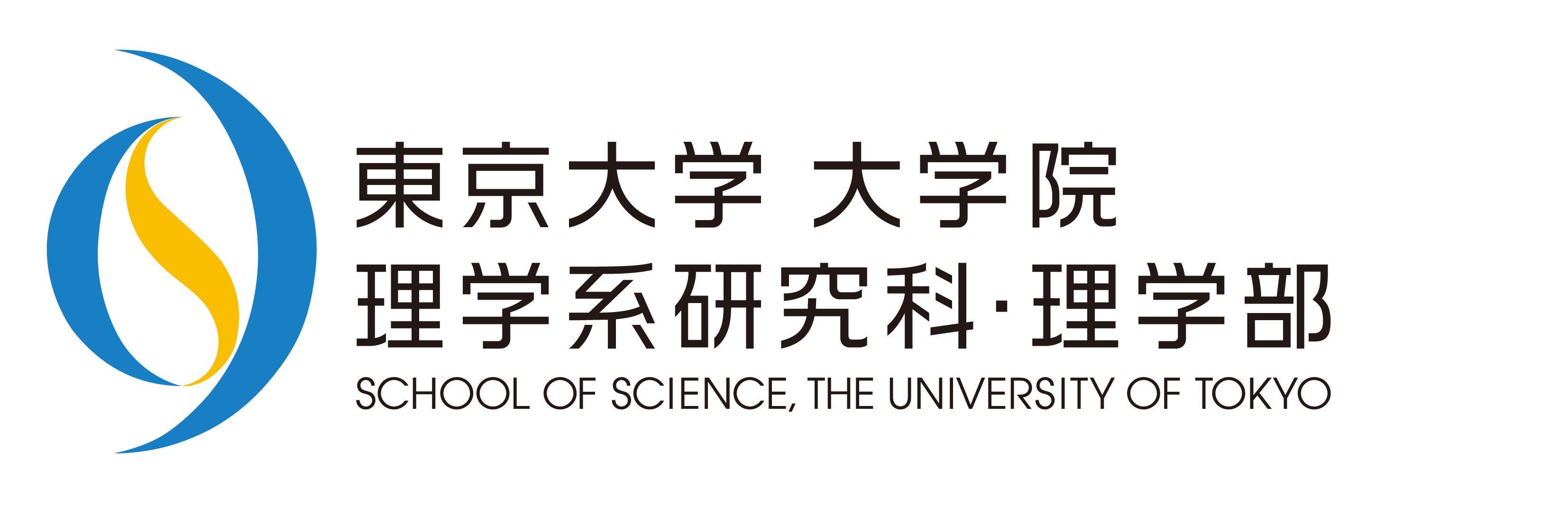高さ300mの津波の痕跡を探す
6600万年前のある日、直径10kmを超える巨大な隕石が地球に衝突した。落下地点であるメキシコのユカタン半島付近は瞬時に1万度の熱波に包まれ、その爆風と衝撃波は周辺1000〜2000kmの範囲を襲い、あらゆるものが蒸発し、あるいは燃え、破壊され、死に絶えた。発生した津波の高さは最大で300mに達し、隕石の衝突によって大気圏外にまで噴き上げられた無数の岩石は火の玉となってこんどは落下し、それらによって大気は300度にまで熱せられた……。
この巨大隕石の衝突が恐竜絶滅の原因となったというのが、天体衝突説である。東北大学で地質学を学んでいた学生時代の後藤和久は、たまたま手にした本でこの天体衝突説について知り、その著者である松井孝典先生(2023年3月22日逝去)と研究がしたいと願うようになる。
「とても面白くて、ワクワクしましたね。こういう研究がしたいなあと思っていたところに、ちょうど松井先生が関わった、天体衝突とその後に地球で起きたことを調べるプロジェクトを東大でやっていると知り、ぜひ加えていただきたいと、東大大学院にやって来たのです」
後藤は懐かしそうにそう語る。
さて、巨大隕石の話はまだ続きがある。後藤自身に語ってもらおう。
「隕石が衝突した瞬間だけでなく、その後に地球に起きた変化のほうが恐竜絶滅にとって大きな役割を果たしました。まず、衝突によって噴き上げられた膨大な量の塵が太陽の光を遮断してしまいます。以前は、少しは光合成もできただろうと言われていたのですが、現在では、計算技術の発達によって、数年間、地上はほぼ真っ暗になったと推測されています。地球は冷え、全球の気温が20度も下がりました。いま、地球温暖化で1.5度上がるというだけでもたいへんだと騒がれているのですが、それどころではなく、地球全体が極寒の環境になってしまったのです。光合成ができなくなって植物は枯れ、それを食べる草食動物が死に、食物連鎖の頂点にいた恐竜はもはや生存できなくなりました。このような状態が、隕石の衝突から10年間ほど続いたのではないかと考えられています」
なんと恐ろしいことか。だが、それでも生命の火は消えなかった。この黙示録的な破滅からの回復のプロセスは次のように進んだ。
「腐食連鎖というものがあります。動物の死骸や植物の枯れ葉などを食べる、ネズミやカタツムリといった生物たちの食物連鎖です。隕石衝突後の地球でも、これらの生物には食糧が供給され続けました。人類の祖先となる小型の哺乳類などは、そうやって生き延びたのでしょう。おそらく5年後ぐらいには日の光も届くようになって、しだいに暖かくなり、植物は地下に埋もれていた種から芽を出し、どんどん環境は回復していったことでしょう。破滅的だったのは最初の数年間だけだったのではないかと、私は思っています」
6600万年前の状況がより正確にわかるようになってきたのは、地球の気候をシミュレーションするモデル計算など、コンピュータ技術の発展によるところが大きいと後藤は言う。そのため、過去の地球の研究からわかったことを、モデル計算によって現在に当てはめてみるということも最近では多くおこなわれる。たとえば明日、地球に隕石が衝突したなら、岩石や塵がどれほど舞い上がるかといったことが予測できるのである。それはとりもなおさず、過去の研究が未来の研究でもあることを意味する。
「我々は、太古の昔にどういうことが起きて、それに対して地球、あるいは生物がどう応答したかというのを読み解こうとします。そんな過去の地球の研究によって、現在の地球温暖化に生物がどのように応答するのかという難しい問題の答が見つかるかもしれません。我々のおこなっている学問の、それが一つの役目であり、貢献ではないかと思っています」
天体衝突説論争で果たした大きな役割
後藤が生まれて初めて訪れた外国がキューバだ。もちろん、巨大隕石に関係がある。
「6600万年前、ユカタン半島は海でした。その時の海底が隆起して、今は地表に出てきています。すると、巨大隕石が衝突したときに海底に溜まった堆積物を今、地上で見ることができるわけです。大学院に入ると、その堆積物を調べるために、キューバの地層調査にさっそく連れていっていただきました。古い地図を頼りに密林の中、道なき道を歩き回って、微妙な地層の変化を探し出すのです」
隕石衝突当時の地球は温暖で、海中には大量のプランクトンが生息していた。白っぽい地層はそのプランクトンを含むもの。隕石衝突後はプランクトンが死滅するので、鉱物の色が主体となり赤みがかった地層となる。その白から赤へと変化している地層を何日もかけて探すのである。地層の境目こそが、隕石衝突の痕跡を含むからだ。
「生い茂る熱帯の植生をかきわけて地層を確かめ、『これは違う』と、また奥へ奥へと分け入っていく感じですね。なかなか見つからず、ほんとうにたいへんでした。何カ所か候補地を見つけ出すのが1年目。そして次の2年目には、キューバ政府から許可をもらって地層のサンプルを採取し、日本に持ち帰って分析をします。すると、『ああ、あれが足りない』などというものが出てくるので、3年目にまた違うサンプルを採取してくる。そんな繰り返しでした」
修士・博士論文のテーマはこの天体衝突説だったが、後藤はとりわけ衝突時に起きた津波にフォーカスを当てた。
「海が大きく攪乱されて土砂が舞い上がり、堆積するということが起きているはずなので、そのプロセスをちゃんと理解したいと思い、隕石衝突後の津波の痕跡を調べるということをしました。攪乱された土砂は、粗いものから先に落ちて、細かいものは後から降ってくるはずなので、地層の土砂の堆積のしかたを見て、それが津波の痕跡かどうかを探るということを始めたのです」
天体衝突説は、地質学の中では今や定説となっているが、そこに至るまでには賛否両論の大論争が続いた。論争決着において重要な役割を果たしたのが、この津波による堆積物が実際に存在するのかどうかだった。博士論文提出から6年後の2010年に、世界中の研究者46人によって、天体衝突説を再確認するという作業がおこなわれた。このとき、隕石の衝突直後の津波のプロセス解明を担当したのが、松井孝典名誉教授と後藤らの日本チームだった。
大地は〝災害〟によってつくられた
6600万年前の津波から現代の津波へと後藤を引き戻したのが、死者が24万人にものぼった2004年のインド洋津波である。
「ちょうどポスドク1年目の時でした。天体衝突説の高さ300mの津波には実感が湧きませんでしたが、多くの方が亡くなったインド洋津波の映像を見て、あれは高さ30mほどだったのですが、こんなことが実際に起こるんだと衝撃を受けました。こういった巨大な津波は過去に頻繁に起きているはずだし、また近い将来起きるに違いないという当然のことを、あらためて思い起こさせてくれました。地球上における津波の履歴、ヒストリーについて地質学的に調べておくことがいかに大事であるかと強く思い、すぐにタイやスリランカに飛んで調査を始めました」
それからわずか7年後に、東日本大震災が起こる。
「起こる可能性が高いことはわかっていました。でも、やはり千年に1度というスケールの大地震が自分のライフスパンの中で起きるということには思いが及びませんでしたね」
もちろん、後藤はこのときの大津波の調査もおこなっている。研究室に置かれた1mほどの厚さの、震災後に仙台周辺で採取した地質試料(コアサンプル)、その縞状に積み上がった地層を指し示しながら、後藤はこう語る。
「ここ(地質試料の最上部)が2011年の津波の後の地表面です。その下が当時あった水田の土壌。その下の黄色の部分は、年代測定によると1611年のもの。伊達政宗が仙台藩を興したころで、直後に津波が来ている、その痕跡がここにあります。さらに下にある白くツルツルした部分が、915年、青森県の十和田湖が噴火したときの火山灰です。十和田湖は実は巨大な火山だったのですね。そして、一番下のほうにあるのが、869年の貞観地震の際の大津波の痕跡です。こんなふうに、わずか1mの厚さの地層の中に千年以上のヒストリーが詰まっているのです。しかも、驚くのは、この地層の半分以上が大災害の時に一瞬で溜まったものだということです。つまり、大災害で積み上がった堆積物の上で、私たち人間が暮らしているということなのです」
しかし、後藤はこうも言う。「災害」というのは人間から見た場合のものであって、地球から見たらそれは「自然現象」にすぎないと。自然はずっと「自然の都合」でいろいろなことを起こしているにすぎないのだと。
「人間が住む世界を人間圏と言いますが、現代では人間圏がどんどん大きくなってきています。すると、地球との接点がより増えてくる。それを私たちは気候変動や環境問題として捉えたり、あるいは自然災害として体験するわけです。私はその〝災害〟と〝自然現象〟とを切り分けて扱い、〝自然現象〟そのものを理解したいと考えています。結果的に、それが〝災害〟を防ぐことにつながっていくと思うからです」
つまり、「人間の都合」ではなく、「自然の都合」から現象を捉えていくことによって、より巨視的かつ正確に「災害」を見つめることができるのだと。

関心は〝破壊と再生のプロセス〟に
マングローブ林や珊瑚礁、そしてはるか彼方の火星もまた、後藤の研究対象だ。それもみな、「災害」を見つめるためである。そして「災害」からの「回復」もまた。
「インド洋津波でタイやスリランカのマングローブ林は壊滅的な被害を受けましたが、この破壊されたマングローブ林はおそらく再生を果たすでしょう。でも、その回復は、いったい何によって決められるのか。生物的な要素の他に、地形や地質がマングローブ林の再生を許容しているのではないか。珊瑚礁の破壊と再生も同様です。石垣島の珊瑚礁も、200〜300年に一度の間隔で大津波に見舞われていることが、研究によってわかっています。巨大隕石による破壊を乗り越えて地球が再生したように、それよりも局所的ですが、このマングローブ林や珊瑚礁の破壊と回復のプロセスにも私はとても興味があるのです。大きなインパクトが地球に与えられ、あらゆるものが一度リセットされて消滅する。けれども、また同じような状態に回復する。はたまた、まったく違う状態へと生まれ変わる。それを決めるのはいったい何なのか。それを知りたいのです」
火星の研究もまた、「地球の歴史をより理解する流れの一環」と後藤は言う。そんな後藤がいま最も力を入れているのが、フィジーやトンガ、フレンチポリネシアといった南太平洋地域の研究である。考古学、民俗学、工学といった分野の異なる研究者たちとの学際的なプロジェクトだ。
「ポリネシアには3300年ほど前から人間が住み始め、ラピタ文化というものが栄えました。16世紀になると、大航海時代でヨーロッパ人がやって来る。そこから文字の記録が残り始めます。それまでは文字による記録がない先史時代ですが、その期間に人々はいろいろな島に移動し、拡散するということを繰り返しています。いったい何がきっかけで移動が起きたのか。どうやらその節目節目で大きな災害が起きていたのではないだろうかと考えられています。そのうちの一つが、15世紀に起きたバヌアツでの巨大噴火で、これはここ1万年の間で最も大きい噴火と言われているものです。その際に巨大津波も起きています。他にも、神話や言い伝えの中に大津波を想起させる話が数多くあります。私は、地層から火山と津波の歴史を明らかにして、そんな先史時代に起きていたであろう大災害の痕跡を見つけ、人々の言い伝えが正しかったのか知りたいと考えています。ポリネシアの災害のヒストリーと、人類のヒストリーと、環境の変化のヒストリー。この3つを同時に明らかにする。そういう仕事をいま始めたところなのです」
現在進行中のこのプロジェクトでは、年に2回ほどポリネシアに赴き、フィールドワークをおこなう。ジャングルの中に分け入って調査するこの仕事はたいへんだが、「楽しいのが先に来ます」と後藤は笑う。ちなみに、いつでもすぐにフィールドワークに出かけられるように、後藤の自宅の自室の本棚には、本の代わりに調査用の衣類やら身の回りのものが整理されて並んでいるそうである。
自分の興味があるものを大事にしよう
地球科学の面白さ、それは時間スケールと空間スケールを自在に変えられるところだと後藤は言う。
「あるときは1億年に1度こういうことが起きますと言いながら、〝巨大隕石が落ちた直後は〟と6600万年前の、わずか1分間のことを同列に話すのが私たちなのです。また、地球全体の話もするし、東京ローカルの話もする。つまり、“時間スケール”と“空間スケール”を自在に操って、過去にも行けるし未来にも行ける。それがこの学問の楽しみの一つなのです」
そんな融通無碍な視点から見えるもの。そこにこそ人類の未来に役立つ何かがあると後藤は考えている。
「おそらく、自分たちが地球に影響を及ぼしているということを理解した最初の生物、それが人間なのだと思います。でも、他の生物は地球への影響など理解せずに地球の環境を変えてきたわけです。たとえば、酸素がほとんどなかった太古の地球を、藍藻や植物プランクトンが酸素のある星に変えたのは、当時からすればとんでもない環境汚染なわけです。だけど、それによってその後の生物の進化が生まれた。それを思えば、今の時代をどう定義づけるかというのはとても難しいことなのです。おそらく、地球はどんなことがあっても存在し続けていくでしょうが、人類が地球上で暮らしていくためには、上手な共存のしかたを見つけることがとても重要です。そのためにも、千年、万年の単位で地球がどう変わっていったのかを知り、理解しておくことが大事だと思いますし、そうすることで人間が進むべき道も少しは見えてくるのではないでしょうか。過去から学んだ知識は、未来への想像につながります。その意味で、過去を語り継ぎ、未来はこうなるだろうという話をすることは、地球科学の責務、私のやるべきことの一つなのかなと思っています」
後藤は少年の頃から、文明の成り立ちや衰退に強く惹かれ、考古学に憧れていた。だが、「進路指導で自動的に高校の理数科クラスに入れられて、そこで初めて、考古学は文系だと知ったのです」と後藤は笑い、こう続ける。
「ああ、困ったなあと思ったのですが、エジプト文明の研究で、石がどこから来たのかとか浸食のしかたでスフィンクスがいつ頃作られたのかを調べる、そういうアプローチを地質学がしていることを知って、地質学もいいかなと思ったのです」
そんな自分の経験を踏まえ、後藤は若者に向けてこんなアドバイスをする。
「自分の興味があるものを大事にすることですね。分野などは、結果としてついてくるような部分でもあります。私も、もしかしたら文学部にいても全然不思議ではなかったと思いますし、キャリアの中では工学に5年ぐらいいたこともありました。自分の興味や関心さえしっかりしていれば、いろいろなところにチャンスがあると思います。そのほうが楽しみながら前に進むこともできるのではないでしょうか。ちなみに、私の研究室に入れば、世界中、いろんなところに行けますよ。文理融合的なテーマも可能です(笑)」
最後にゴールは何ですかと訊ねると、こんな答えが返ってきた。
「考えたことはないですが、そうですね、人類の歴史の本の中に何行か、私が知ることができたことを書き込めたら、それだけで満足ですね」
※2023年取材時
取材・文/太田 穣
写真/貝塚 純一


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)