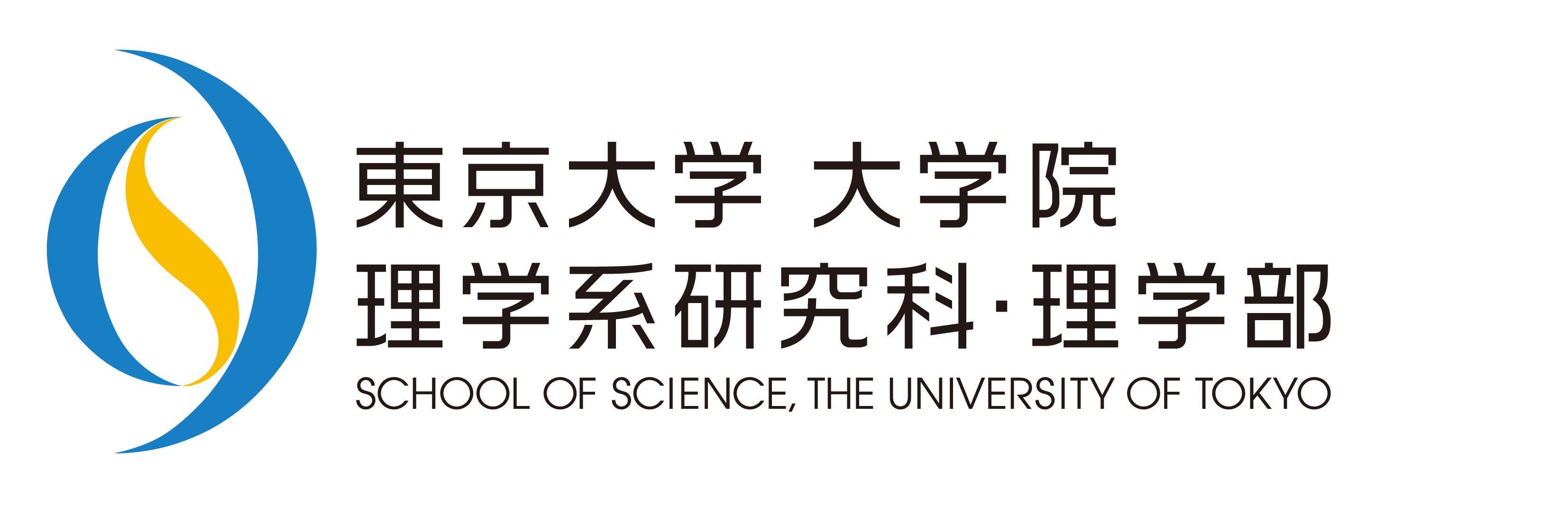11歳で出会った
アポロ17号の船長
「宇宙飛行士になりたいって中学や高校の時にはまわりにずっと言っていて、ですから中高の友だちは『やっと宇宙飛行士になれるね』とみんな喜んでくれましたが、大学以降は宇宙飛行士への夢はほとんど公言してきませんでした。なんていうか、30歳、40歳になって『実は宇宙飛行士になりたい』と言うのは照れくさいところがあって。それに自信もまったくなかったですし」
これまでで最年長の46歳にして、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士候補者に選ばれた諏訪理さんは、そう言ってまさに照れくさそうに笑った。
諏訪さんは東大理学部の地学科*出身。
「日本人の宇宙飛行士には工学部や医学部出身の人が多くて、理学部出身は今のところ毛利衛さんに続いて私が二人目なんです」
東大を卒業後、米国留学を経て世界気象機関(WMO)、世界銀行といった国際機関で仕事をしてきたが、そのあいだもずっと宇宙飛行士への夢を心の奥深くに、しかも強く抱き続けてきたという。だから、もちろん、2008年に始まった前回の宇宙飛行士候補者選抜試験にも挑戦をした。
「むしろ2008年の時のほうが根拠の無い自信があった気がします(笑)。今回に関してはほんとうにまったく自信がありませんでした。ですから合格の連絡をもらったときは驚きました。とにかく、びっくりしました。その日は興奮してほとんど眠れませんでしたね」
茨城県のつくば市で育ち、サッカーと野球が大好きで、近所の森や林でクワガタやカブトムシを捕り、夜は田んぼのカエルの合唱を聞きながら眠っていた諏訪少年が宇宙飛行士を夢見たのは、小学5年生、11歳の時のこと。本物の宇宙飛行士に会ったのがきっかけだった。しかも月に行って月面に降り立った宇宙飛行士だ。その人の名をユージン・サーナンといい、アポロ17号の船長である。
「子ども向け科学学習雑誌の作文コンクールに応募したら入選して、そのご褒美として他の子どもたちと一緒に、アメリカのNASA関係の施設を回るという旅行に連れていってもらったんです。ワシントンD.C.のスミソニアン博物館、フロリダのケネディ・スペースセンター、アラバマのマーシャル宇宙旅行センター。そしてヒューストンのジョンソン・スペースセンターで当時まだご存命だったサーナンさんにお目にかかって、いろんなお話を聞かせてもらいました。この時が、初めて宇宙飛行士という職業を意識した瞬間だったと思います」
つまり、これは35年かけて叶えた夢なのである。
*現在の地球惑星環境学科
祖父の影響で芽生えた
地球科学と国際開発への関心
宇宙飛行士への夢を抱く前から、科学は大好きだった。それは諏訪さんの父親が理系の研究者であり、かつまた、つくばという町が研究所の多い場所だったという環境が、大きく影響しているかもしれないと言う。理学部で地学科を選ぶ動機にもなった、地球や太陽系の歴史といった壮大なスケールの物語への関心は、少年の頃にテレビで見たNHKの『地球大紀行』という番組の影響だ。
「太陽系や原始地球がどうやってできたのかということを映像で見せてくれるのですが、空間と時間のスケールの大きさに魅せられました。何の変哲もない一個の石からも地球の大昔の歴史を物語ることができるということにも感動しましたね」
加えて、マレーシアの大学で教鞭を執っていた祖父の影響もあった。
「祖父は戦後、気象庁に勤め、その後マレーシアの大学で大気科学、大気環境マネジメント的なことを教えていました。そんな祖父が年に1回、日本に帰ってくるといろいろな話をしてくれました。それは祖父が亡くなる、大学4年のときまで続きました。わたしが後に地球環境や途上国との接点がある仕事についたのは、そんな祖父の影響がとても大きかったと思います」
祖父が関わった国際開発という分野への関心、地球という惑星の壮大な歴史への興味、そして宇宙飛行士への夢を胸に抱きつつ、まずは理系の研究者になるべく東大理学部に入学した諏訪さんだが、進振りで地学科を選んだのは、いわばそのすべての可能性を叶えたいがためでもあった。
「なんといっても地球科学がやりたかった。さまざまなところに行ってさまざまなものを見るという、フィールドに出てそこから物語を作るということに憧れ、フィールドワークが多いイメージのあった地学科を選びました。もう一つは、アポロ11号から17号まで、12人の宇宙飛行士が月面に降り立っているのですが、そのうちの11人は軍関係の人なのです。でも、ただ一人だけ科学者がいた。それがハリソン・シュミットさんというアポロ17号のクルーで、彼は地質学者だったのですね。それが頭の片隅にあって、地質学は宇宙飛行士という夢と無関係じゃない、と思ったのもありました。とにかく、進路を選択するときにはいつも、宇宙に行く夢をあきらめないですむような、そんな可能性を保持できるようにしておこうという気持ちでいました」
地学科での一番の思い出は、やはりそのフィールドワークだった。
「東大の演習林がある千葉県の清澄山で、沢を伝いながらどんな地層かをプロットしていくという、学部3年生のメイン授業があって、これは1週間ぐらい泊まり込んでおこなうものなんです。その沢にはヒルがたくさんいて、みんな必ずそのヒルにやられるんですよ。それが一番の思い出として残っていますね」
米国への留学と
南極でのフィールドワーク
東大理学部を卒業した諏訪さんは、アメリカのデューク大学へ留学。修士課程で環境マネジメントを学ぶ。
「マレーシアにいた祖父から、早いうちに留学をしたほうがよいとずっと言われ続けてきたのが心の中にあったのと、アメリカへの漠然とした憧れみたいなのがあって、なんとなくアメリカ留学はかっこいいみたいな薄っぺらい理由もどこかにはありました(笑)。もちろん、国際的な場で働きたいという思いもあったので、英語を話せるようになりたいという気持ちもありましたし」
留学当初はやはり言葉で苦労をしたという。
「アメリカの授業では、パティシペーション(participation)といって、どれだけ授業中に発言したかが評価されるので、それがすごいプレッシャーでした。最初は、指さないでくれって授業中祈っていましたが、そのうち開き直ってきて、話の途中からだとついていけなくなるので、なるべく最初の方に自分から発言するとか、いろいろと策を弄していました(笑)」
修士課程を終えると、諏訪さんは「さらに学ぶために、怠けずに努力せざるを得ない状況に身を置きたい」と、プリンストン大学の博士課程に進み、気候科学を研究する。入学時のオリエンテーションで、博士課程修了までに一人平均2回はカウンセリングを受けざるを得なくなるから覚悟するようにと言われ、「すごいところに来ちゃったなあ」と不安になったそうである。
「いま振り返ってみると、当時はノーベル賞を受賞した眞鍋淑郎さんもいらっしゃいましたし、プレートテクトニクス理論を立ち上げたグループの先生も現役として残っていましたし、ひじょうに刺激的な環境でしたね。プリンストンに行ってよかったなと思います」
そのプリンストンでは南極にも行った。南極の氷床コア(試料として掘削した円形状の氷)を使って太古の気候変動を復元するという研究のためだ。2カ月と少しの滞在だった。
「ずっと地平線まで雪で覆われていて、風が吹くとふわふわっと雪が舞い上がる。それが大地に白い靄がかかっているように見える。そこには見わたす限りの白と青の二つの色、それと太陽だけがあるというシンプルな光景でしたが、ほんとうにきれいで、雄大で、地球上にこんなところがあるんだと、心から感動しました」
アフリカの〝現場〟から
国際機関の〝現場〟へ
博士課程を終えると、諏訪さんはJICA(国際協力機構)の青年海外協力隊の一員としてアフリカのルワンダへと赴く。
「大学院で地球科学を学んだのは、これが国際開発に繋がるかもしれないという思いがあったからでした。私が大学に入った1995年ころにはすでに気候変動の問題が大きく取り上げられ始めていて、1997年には京都でCOP3(第3回気候変動枠組条約締約国会議)が開催されました。そのころから、環境問題、気候変動の問題は、今後国際開発でも重要な課題になってくるだろうなと思っていました。そういう予感があって地球科学を研究したわけですが、博士課程を終えて、この知識を国際開発的なところでどう活かしていくかと考えたときに、お手本となるような人が周囲にいなかったので、どうしたらいいのかわからなかったのですね。そこで、とにかく現場を見ようと。教育は間違いなくどの分野でも大事なことだから、2年ほどアフリカに行って教育にたずさわってみようと思い、飛び込んでみたのです」
ルワンダでは午前中に中学と高校で理数科を教え、午後には大学の理学部で教壇に立った。そこで、ひたむきな情熱を持つ建設的な若い世代の人々に共感すると同時に、科学的データを取ってそれをもとに政策を作る、という当たり前のことができない発展途上国の政治の現状も垣間見た。都市化が進み、大気汚染の問題が大きくなっているアフリカ。そこでは、地球科学や環境科学を学んだ人間が貢献できる場面がたくさんあることを、諏訪さんは肌で感じたのだ。
「ただ、現場でできることの面白さと、現場ではできないもどかしさというのも感じました。ではどうすべきかと考えたとき、やはり国の政策レベルから始めなければいけないのかと思いました。とはいえ、国際機関にしろ、JICAのような援助機関にしろ、やはり外部者でしかないので限界はあるのですが、それでも国際機関的な立ち位置から開発に関わってみたいと考えたのですね。そこで、自分の専門の地球科学に近い専門機関である世界気象機関(WMO)というところで働くことにしました。国際機関というのはどういうふうに動いているものなのか、そういう勉強もしようと思ったのです」
世界気象機関ではジュネーブの本部で2年、アフリカのケニアで1年半働いた。日本の国交省や気象庁にあたる途上国の気象水文機関の能力を強化し、向上させるのが仕事だった。正確な気象情報を迅速に多くの人に届けることができれば、それは途上国の農業や防災に大きく役立つのだ。
その後、ちょうど気候問題への関わりを積極的に開始していた世界銀行が日本人採用ミッションをおこなっていることを知った諏訪さんはこれに応募し、2014年に採用される。途上国の気象・気候・水文サービスを強化するプロジェクトが諏訪さんの担当となった。
そして、2023年2月28日、あの合格発表のその日まで、諏訪さんは弱い立場にある人々の防災や水供給などのための仕事を懸命に続けてきたのである。
月を一つのステップに
次は火星探査へ
宇宙飛行士として一番行きたいところ、それはもちろん月だと諏訪さんは言う。
「地学を勉強したのは、やはり月に行きたいという思いがどこかにあったからです。もちろん火星にも行ってみたいです。比較惑星学という分野にもとても興味がありましたし、火星と地球とではそれぞれの気候史がどこでどんなふうにして分かれ目ができたのかということは、多くの人が興味あることだと思います。地球を知るには火星を知ることが重要です。地球科学をやってきた人間として、月を一つのステップとして、次に火星探査に関わることができれば面白いなって思いますね」
諏訪さんは「自分が本当に夢中になれるもの、好きなものを見つけることがとても重要で、好きで夢中になれるからこそ一生懸命にできる」と言う。
「そういう意味では、東大は最初の2年間の教養学部でいろいろなことを見てみる機会があるので、ひじょうにいいシステムだと思います。それに、東大はやっぱり素晴らしい先生がさまざまな分野にいらっしゃるし、それがとても刺激的だし、同級生や先輩にも素晴らしい人がいっぱいいる。自分の知的な好奇心を満たしてくれるものがたくさんあるところですね。あとはそれを自分でどうプロアクティブに、積極的に使っていくのかが大事です。若い人たちには、いまはどの分野でもさまざまな新しい可能性が広がっているので、ぜひ頑張ってほしいなと思います」
その好きで夢中になれたものが、偶然にも1枚の有名な写真の中に凝縮されていると諏訪さんは言う。それは、ブルーマーブル(青いビー玉)と言われる、アポロ17号が1972年に地球からおよそ4万5000kmの距離から撮影した、漆黒の宇宙に浮かぶ美しい地球の姿である。
「あのブルーマーブルの真ん中に映っているのはアフリカなんですね。下の方には南極も映っています。しかも、あの写真は私の宇宙飛行士への夢のきっかけを作ってくれたサーナンさんが乗り組んでいた宇宙船から撮られた写真なのです。私の人生のいろんなものがギュッと詰まった1枚だなあと、ふと思ったりするのですね」
地球とは宇宙にたった一つの、しかもとても脆弱な存在であることを人間に教えてくれたあのブルーマーブルの写真は、アポロ計画の大きな財産だと諏訪さんは言う。かけがえのない惑星──地球というブルーマーブルの視覚的イメージは、その後の環境問題の議論においても、人類の深層心理に大きな影響を与えたのではないかと諏訪さんは考えている。
おそらく、そのブルーマーブルを、諏訪さんは何年後かにその目で実際に見ることになる。
「見たら、感動するだろうなとは思います。でも、実際にどんな感情が自分の心に湧くのだろうか、今はわかりません」
そう言って、諏訪さんはちょっとだけ遠くを見つめるような目をした。
※2023年6月7日取材
文/太田 穣
写真提供/JAXA


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)