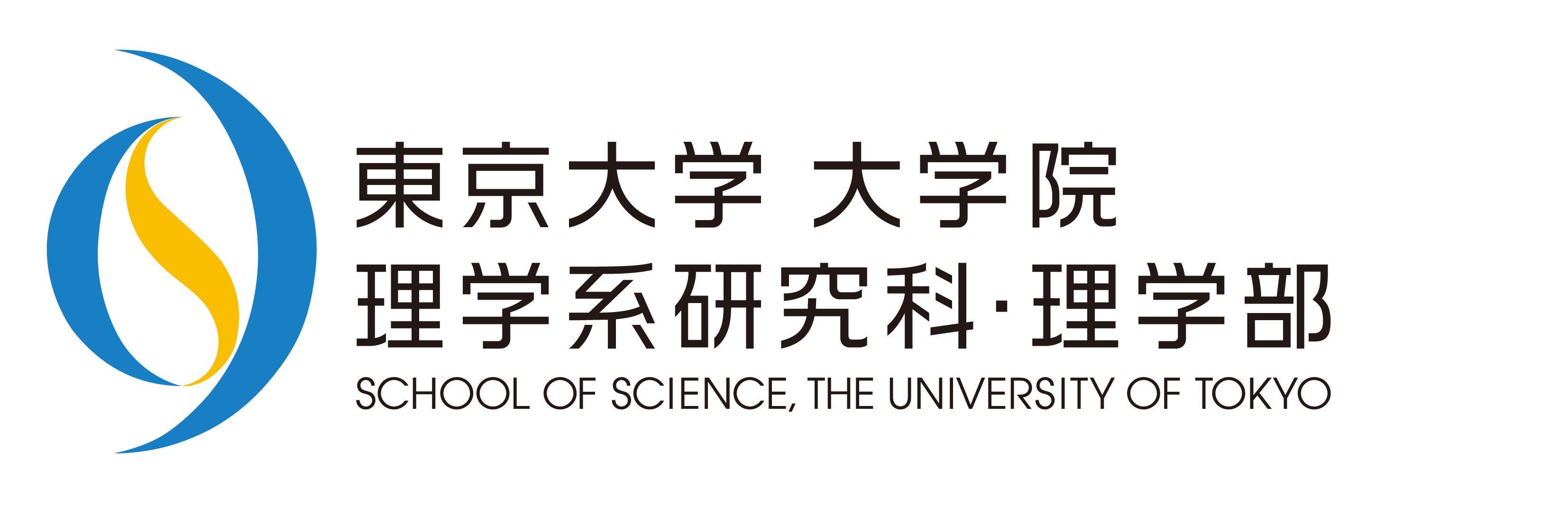生命を分子レベルで照らす
世界の謎を解き明かすため、科学者たちは何百年も前から光を利用してきた。17世紀の顕微鏡の発明を境に、人類は肉眼の限界よりもはるかに小さいものを見ることが可能となった。生物学において、光は単に「観察のツール」だけではなく、分子レベルで生命を制御し操作する方法としても、重要な役割を果たしている。
光に反応する遺伝子組み換えタンパク質を使った光遺伝学(optogenetics)は、青色や赤色のパルス光で特定の神経細胞(ニューロン)の活性を制御することで、21世紀の神経科学に革命をもたらした。
またニューロン活動の観察や、生きた細胞内の分子の動きを高精度で追跡するためのツールとして、蛍光バイオセンサーが作られてきた。しかし、こうした進歩の半面、既存の蛍光バイオセンサーには、光が暗すぎるものもあれば、応答速度が遅すぎるもの、生体組織の深部で検出できないものなどの限界もあった。
そこで登場するのが『化学遺伝学(chemigenetics)』である。この新しい研究分野は、合成化学とタンパク質工学を融合させ、次世代のバイオセンサーを創製する最先端のアプローチだ。従来の蛍光タンパク質やバイオセンサーが完全に遺伝子にコードされているのとは異なり、有機合成した蛍光色素を、遺伝子組み換えタンパク質でできた骨格に埋め込むハイブリッドな手法を採用している。その結果、優れた輝度と感度を持ち、生体組織のより深部でも検出できる新しいバイオセンサーが誕生しつつあるのだ。
この分野の最前線にいるのが、東京大学理学部化学科の生体分子化学者、ロバート・アール・キャンベル教授だ。彼の研究は、脳機能や代謝における重要なシグナル伝達物質であるカルシウムイオン(Ca²⁺)とカリウムイオン(K⁺)の化学遺伝学センサーを開発し、バイオイメージングの限界の先へと挑んでいる。特に赤色~近赤外光を発するセンサーを設計することで、これまで以上に脳の深部を観察し、やがては神経活動や病気のメカニズム、さらには意識そのものを研究するための新たなツールを作り出そうとしている。

従来のセンサーを超えて: 化学遺伝学の誕生
バイオイメージングの歴史は『蛍光』と深く絡み合っている。1960年代に生物学者の下村脩博士によって、オワンクラゲ(Aequorea coerulescens)由来の緑色蛍光タンパク質(GFP)が発見され*、その約30年後の1990年代初頭にGFP遺伝子が単離されて以来、研究者は蛍光タンパク質を使用して細胞の構造や機能を解明してきた。遺伝子コード型蛍光バイオセンサーとは、特定の分子と相互作用すると蛍光を放つよう改変された遺伝子組み換えタンパク質で、カルシウムシグナル伝達、代謝、遺伝子発現などの生物学的プロセスを追跡するために重要な役割を果たしてきた。
*2008年ノーベル化学賞受賞
GFPやその改変タンパク質をもとに作られたセンサーは数多くのブレークスルーをもたらしてきたが、それらは完璧ではない。これらのタンパク質の多くは、可視光領域の青~緑色の範囲で発光し、生体組織に強く吸収されるため、深部組織の観察は困難だ。また、輝度が低い、応答時間が遅い、特異性に乏しいなどの欠点もあるからだ。
この状況の打開策となったのは、化学遺伝学という新しいアイデアだった。化学遺伝学蛍光センサーは、天然の蛍光タンパク質のみに頼るのではなく、有機合成した蛍光色素と、それに結合する自己標識タンパク質を使用する。それにより、バイオイメージングに新たな可能性を吹き込むことに成功したのだ。
「このアプローチにより、研究者はタンパク質の限界を超えて、化学者が実験室の中で設計して作った合成部品と、タンパク質を組み合わせた新しいシステムを作ることができます」

HaloTagシステム: ハイブリッド蛍光センサーの鍵
化学遺伝学における重要な技術の一つに、合成蛍光色素と選択的に結合するように設計された自己標識タンパク質であるHaloTagシステムがある。従来の蛍光タンパク質は、それぞれ固有の蛍光波長を持つのに対し、HaloTagを基盤とするバイオセンサーは、さまざまな蛍光色素と自由に結合させることができるため、多様なイメージング用途へ応用できる。
カリウムイオン(K⁺)のイメージング研究では、キャンベルらが最近、HaloTagタンパク質とK⁺結合タンパク質(Kbp)とを融合させて開発した、初の化学遺伝学K⁺センサーである「HaloKbp1シリーズ」によって、蛍光色素の細かい選択が可能になっている。このセンサーは、化学遺伝学センサーの特徴である特異性と輝度に優れており、これを用いれば、K⁺の動きをリアルタイムで追跡することができる。
K⁺とは、ニューロンの興奮性と細胞の恒常性を維持するための核となる物質だ。K⁺シグナル伝達の異常は、てんかん、脳卒中、神経変性疾患など、さまざまな神経学的状態に関連している。キャンベルらの研究は、生体内におけるK⁺の動きを正確に可視化し、神経回路がイオンの恒常性をどのように調節し、電気的活動に応答しているのかを理解するための重要なツールを提供した。
「光遺伝学が通常、光を利用して生物学的プロセスを正確にコントロールすることを目標とする一方で、私たちの研究の多くはこれらのプロセスを可視化して分析することに焦点を当てています」と、キャンベルは話す。「この2つは本質的に結びついています。光による操作を行っても、その影響を観察する方法がなければ意味がありません。私たちは、生物の活動を制御するだけでなく、その複雑な結果をリアルタイムで明らかにすることを目指しています」
カルシウムと神経科学: 脳活動を可視化する
カリウムが細胞の安定性にとって重要なのに対し、カルシウム(Ca²⁺)にはニューロンにおけるシグナルの伝達という重要な役割がある。ニューロンが発火するたびに、細胞内のCa²⁺濃度は急上昇し、神経伝達物質の放出、シナプス活動、さらには遺伝子発現までもがコントロールされる。こうしたCa²⁺シグナルの波は、記憶、認知、学習の根本までも担っているのだ。
「GCaMP*のような従来の遺伝子コード型Ca²⁺センサーは、神経科学で広く使われてきました。しかし、これらのセンサーは、深部組織でのイメージングには不向きなのです」とキャンベルは述べる。さらに、多くの光遺伝学的ツールは活性化のために青色光を使用するため、GFPを使った蛍光センサーだと、イメージングと光刺激を同時に行うのが難しいという問題もある。
*緑色蛍光タンパク質(GFP)を基盤とする、代表的なCa²⁺蛍光センサー
近赤外蛍光の役割
イメージングの解像度を最適化し、光遺伝学的ツールとの干渉を減らすために、キャンベル研究室では赤色~近赤外蛍光に焦点を当てている。従来のバイオセンサーは、生体組織に強く吸収される上に、自家蛍光を発しやすい青~緑色の波長範囲で動作する。これをより長い(=赤色に近い)波長にシフトさせることで蛍光信号がより明瞭になるだけでなく、内因性の蛍光物質からの干渉も低減される。その結果、イメージングの品質が向上し、組織のより深いところまで可視化できるのだ。
「簡単に言えば、赤ければ赤いほど良いのです」とキャンベルは言う。近赤外蛍光タンパク質(NIR-FP)、あるいは遠赤色の蛍光色素で修飾した化学遺伝学タンパク質を基にバイオセンサーをつくることで、彼らは蛍光イメージングのSN比を最適化して、神経活動や代謝活動を、より効果的にリアルタイムで検出できるようにしている。
この赤色方向への波長シフトは、光を使って正確にニューロンの活性を制御することが必要な光遺伝学にとって特に重要だ。多くの光遺伝学的ツールは青色領域で動作するため、赤色の蛍光センサーを使用すれば、イメージング光と刺激光との干渉を防ぐことができる。これにより、研究者はニューロンを活性化すると同時にその応答を観察できる。
脳内の代謝の追跡
「神経科学者は、おそらく宇宙でもっとも複雑な構造である脳の研究という課題に突き動かされているため、新たな技術の導入に貪欲なのです」キャンベル研究室では、カルシウムイメージングにとどまらず、乳酸やグルコースなどの代謝物に対する蛍光センサーを開発して、神経ネットワーク全体でエネルギーがどのように分布しているかを研究している。中でも乳酸は、周囲の細胞からエネルギーを必要とする細胞へと代謝エネルギーを運ぶ、重要なシャトル分子として考えられつつある。
「乳酸は、例えるなら脳内エネルギーの世界における通貨のようなもので、脳内の必要な場所を往復する必須媒体だという仮説があります」とキャンベルは説明する。彼らが作った蛍光センサーを用いてこれらの『取り引き』をリアルタイムで追跡することで、研究者は神経活動と代謝需要との関連性を調べることができるのだ。
キャンベルらは、さらにカルシウムセンサーと代謝物センサーとを組み合わせることで、神経科学におけるもっとも重要な課題を明らかにしようとしている。つまり、脳が電気的活動とエネルギー消費のバランスをどのようにとっているかを包括的に把握し、常に変動するエネルギー需要を脳がどのように満たしているかを調べるのだ。
「私たちが開発したカルシウム蛍光センサーは、代謝の研究でも非常に重要です。なぜなら、脳内でニューロンが発火したり、ホルモンが細胞表面の受容体に結合したりといった、ほぼすべての細胞シグナル伝達過程において、細胞内のカルシウム濃度が変化するからです」とキャンベルは話す。ニューロンが発火すると、代謝エネルギーの即時かつ正確な供給が必要になる。キャンベルらの研究により、研究者はニューロンの活動だけでなく、それを維持する代謝経路も追跡できるようになる。その結果、神経シグナル伝達に応答してグルコースや乳酸がどのように動的に利用されるかについて洞察できるのだ。
「最近の神経科学では、ニューロンがその活動に必要なエネルギーを、必要な場所とタイミングでどうやって得ているのか、という疑問が注目されています。この研究はそうした問題の解決に貢献するでしょう」
実際に、アルツハイマー病、パーキンソン病、てんかんなどの神経変性疾患では、エネルギー代謝やイオン調節の異常が認知機能障害や運動機能障害に先行すると報告されているため、この研究はこうした疾患を理解する上で特に重要となるだろう。ニューロンとグリア細胞*がどのように相互作用するか、また脳内で各代謝物がどのように利用されるかを可視化することで、キャンベルらの研究は、代謝バランスの回復を目的とした神経疾患の新たな治療戦略に繋がるかもしれない。
*ニューロンの周りにあり、その働きを助ける細胞
バイオセンサーの未来
化学遺伝学は有望とされているにもかかわらず、依然として大きな課題に直面している。蛍光色素やキレート剤などの合成分子を、その安定性を維持しながら効率的に生体組織に送達しなければならないからだ。特に神経科学への応用には、血液脳関門と呼ばれる、ほとんどの外来分子が脳に侵入するのを防ぐために生物が持つ高性能な防護壁を突破する必要がある。
キャンベルはこのハードルを認め、このプロセスを治療薬の吸収になぞらえて言う。「合成分子を薬のように投与して、動物の体内に入れなければいけません。つまり分子を注射して、理想的にはそれが直接脳に行く必要があるのです」
しかしキャンベルは、これらのハードルが克服されたとしても、マウスなどの哺乳類で化学遺伝学蛍光ツールを使用するには、まだ大きな障害があると考えている。
「近赤外光であっても、組織は比較的不透明で、蛍光イメージングの深さはせいぜい数百ミクロンまたは数ミリメートルに制限されています。私たちは、光だけに頼らず、より深いイメージングを可能にする新しい分子イメージング技術を開発する必要があります」
この目標に向けて世界の研究者たちは、光を当てて音波を生成させることでより深いイメージングを行う光音響センサーや、体への負担が少ない超音波応答性バイオセンサーなどの代替イメージング技術を模索している。MRI用のバイオセンサーも開発が進んでおり、蛍光以外の方法で脳活動を追跡するためのフロンティアが拓かれつつある。
好奇心と粘り強さ: 科学的発見の核心
研究はしばしば予測不可能で、実験は成功するよりも失敗することが多く、根本的な疑問への答えはいつまでたっても捉えどころがない。科学者としてのキャリアを考えている世界中の学生にとって、前途は多難に思えるかもしれない。しかし粘り強く取り組めば、科学は、知識の限界を押し広げ画期的な発見に貢献する、という唯一無二の機会をくれるだろう。
キャンベルはこの事実を身をもって理解している。彼の科学探求への旅路は、カナダで始まった。キャンベルは自身で立ち上げた研究室で生物分析化学の研究に従事した後、日本の東京大学へ移り研究を続けている。長年にわたり、彼は学際的なアプローチを採用し、合成化学、分光学、分子生物学、神経科学を統合して、最先端のバイオイメージングツールを開発してきた。
「科学者としてもっともやりがいを感じることのひとつは、博士号を取得する頃には、あるトピックに関する世界的な専門家になっていることです。君は、“自分の研究について世界一詳しく知っている”のです」と目を輝かせてキャンベルは話す。
彼のようなキャリアを目指す学生に対して、キャンベルは好奇心、粘り強さ、そして適応力の重要性を強調する。今日の科学的な探求は、もはや従来の学問境界に限定されず、化学、生物学、物理学がますます交差する形でイノベーションを推進している。
「私たちには、分野間を自在に横断できる人が必要です。生物学はもはや生物学だけではありません。それは化学であり、物理学であり、工学なのです」
イノベーションのハブ
東京大学でのキャンベルの研究は、こうした学際的なアプローチを反映している。化学遺伝学とバイオイメージングにおける彼の研究は、さまざまな分野の専門家との共同研究を通して得られたものである。また留学先を考えている学生にとっても、東京大学とは理想的な環境にあるからだ。
「ここは、人々が問題にアプローチする新しい方法を常に考えている場所です。各分野の最前線にいる研究者が揃っています」

彼はまた、研究は国際的な取り組みであることを強調する。科学は国境を越え、異なるバックグラウンドや視点を持つ研究者との協力が進歩に不可欠だ。彼自身のブレークスルーの多くも、世界中の共同研究者と協力することで生まれたものだ。
好奇心に従い、リスクを恐れずに———。キャンベルは科学を志す若い旅人に向けて力強いメッセージを送る。
「科学とは探求です。まずは手広く、やがてはニッチに」
研究は必ずしも計画通りに進むとは限らないが、挫折は前に進む過程の一部だ。大切なのは、モチベーションを保ち、問い続けることだと。
次世代の科学者は、今日の発見に基づいて、新しいツールを開発し、我々がまだ想像もつかないような数々の問題を解決するだろう。バイオイメージング、神経科学、合成生物学。どれを取っても、科学の未来は、知の限界に挑戦する意欲のある若い研究者たちにかかっている。
化学と生物学の横断に挑戦する覚悟のある者にとって、旅は今ここから始まる。
※2025年取材時:英語取材・文:森 旭彦(訳:寺井 琢也・柳町 拓海・今井 渉世)
撮影/貝塚 純一
文章は簡潔にするために編集されています。


![リガクル[rigaku-ru] Exploring Science](/ja/rigakuru/images/top/title_RIGAKURU.png)